塾の開業において「どこに出店するか」は経営の成否を分ける重要な要素です。本記事では塾の開業における「立地」の観点から、失敗しないための立地選びのポイントや、避けるべきリスク、立地に応じた成功戦略までを徹底解説。これから塾を開業しようと考えている方、物件選びに迷っている方にとって、判断軸を明確にするための実践的なガイドとなっています。
塾の立地が経営を左右する理由とは

立地は集客力・家賃負担・運営スタイルなど、塾経営に大きく影響します。ここではその影響と重要性を具体的に掘り下げていきます。
集客における立地の影響とは
塾の集客は立地に大きく左右されます。たとえば小学生を対象にした塾では、自宅から徒歩や自転車で通える住宅街立地が人気です。一方で高校生対象の場合は駅チカなどの通学経路上が効果的。実際、駅徒歩1分の場所に教室を構えた個別指導塾では、開業初年度から生徒数が30名を超えるなど、アクセスの良さが集客に直結した例もあります。ターゲット層の動線と生活スタイルを意識した立地選びが重要です。
固定費や通塾利便性にも直結する
塾の家賃は月々の固定費として大きな割合を占めます。駅近物件では坪単価が2~4万円になることもあり、広さによっては月30万円以上になる場合も。一方、郊外では坪1万円台で借りられることもあり、経費を抑えやすいメリットがあります。また、駐輪スペースの有無や車での送迎導線も保護者にとって重要な判断材料。家賃だけでなく、通いやすさや保護者目線での利便性を含めた総合的な判断が求められます。
成功している塾に共通する立地傾向
成功している塾の多くは、①ターゲット層の生活圏に近い、②視認性が高い場所にある、③送迎や通塾がしやすい環境という3つの共通点を持ちます。例えば住宅街の入り口付近にある塾では「近くて安心」との声が多く、長期的な通塾につながりやすい傾向があります。また、夜間も明るく安全な道沿いにある立地は、保護者からの信頼も得やすい要素です。単に安い・人通りが多いではなく、地域特性を活かした配置が重要です。
塾開業で避けるべき立地の特徴とその理由

ここでは「人通りが多い=好立地」とは限らない落とし穴や、治安や競合状況など、立地選びで見落としがちなリスクに注目します。
人通りが多くても塾に向かない立地とは
一見すると集客に有利そうな駅前や繁華街でも、塾には不向きなケースがあります。たとえば、カラオケや飲食店が多い通り沿いは騒音や治安面の不安から保護者の印象が悪くなりやすいです。また、飲み屋街が近いエリアでは夜の雰囲気が悪く、夜間通塾が多い中高生の保護者から敬遠されることも。人通りの多さだけでなく、周辺環境の質を見極めることが大切です。
周辺環境(騒音・治安・交通事情)から見るリスク
塾周辺の騒音や治安は、保護者にとって通わせるか否かを左右する大きな要因です。たとえば、交通量の多い幹線道路沿いでは騒音で授業に集中できなかったり、送迎時の安全性に懸念が出ることも。また、街灯の少ない裏道や、治安が悪いとされるエリアは保護者からの信用を得づらくなります。開業前には、実際に昼夜の時間帯で現地確認を行い、治安や交通状況も必ずチェックしましょう。
競合が多すぎるエリアは本当にNG?
同業塾が多いエリアは一見レッドオーシャンに思えますが、需要が多い裏返しでもあります。たとえば大手塾が多く並ぶ駅周辺であっても、個別指導や補習に特化した塾で差別化することで、ニーズを捉えて成功している例もあります。問題は「競合の多さ」そのものではなく、「自塾の立ち位置」が明確であるかどうか。競合分析とポジショニングによって、むしろ競争がある地域をチャンスに変えることも可能です。
立地選びで押さえるべき5つのチェックポイント

ここでは、塾開業に先立って必ず確認すべき立地選びの観点を5つに整理し、順を追って紹介していきます。
ターゲット層の人口・世帯構成を確認する
塾の成否は、その地域にどれだけの「対象となる子ども」が住んでいるかに大きく左右されます。出店エリアの人口動態や年齢別構成、共働き世帯の割合などを調べることで、継続的なニーズが見込めるかを判断できます。市区町村の統計データや国勢調査、自治体のHPなどを活用し、数値に基づいた判断を行いましょう。
塾・学校・住宅地などの距離関係を見る
ターゲット層の生活圏に、どれだけ自然に入り込める立地かを見極めることも重要です。学校からの帰宅動線上や、住宅街の入口付近などは塾に適した立地です。Googleマップなどで周囲の学校や競合塾との位置関係を調査し、地図上で自塾が選ばれる理由を可視化しましょう。過不足なく適度な距離感がポイントです。
送迎や通塾のしやすさ(駐輪・交通導線)を考慮
特に小中学生の通塾では、保護者の送迎しやすさが集客を左右します。車を停めやすい道路環境や、駐輪場の確保は保護者にとって安心材料です。また、駅やバス停からの導線が分かりやすいかも重要な視点。送迎時のトラブルを避けるためにも、実際の通塾シーンを想定しながらアクセス性を確認しましょう。
賃料・坪単価などコスト面の妥当性を比較
開業初期は固定費を抑えることも大切です。エリアごとの坪単価相場を把握し、自塾の経営モデルに合う物件を選びましょう。たとえば駅前なら坪単価2〜4万円、郊外なら1万円台というケースも。家賃が高くても集客が見込めるなら投資価値がありますが、収益とのバランスを見て慎重に判断する必要があります。
将来的な需要変化も視野に入れる
立地選びでは現在の環境だけでなく、今後の変化も視野に入れることが重要です。たとえば再開発により駅周辺の人口が増加する可能性があるエリアや、新興住宅地が造成される地域では、将来的な需要の拡大が期待できます。一方で、少子化や学校統廃合の影響が懸念される地域では慎重な判断が求められます。
立地に応じた塾スタイルの工夫と成功事例

ここでは立地特性ごとに異なる塾の運営スタイルや成功の工夫を紹介し、場所に合わせた最適な展開方法を探ります。
駅前・繁華街型:流動人口を活かした対策
駅前や繁華街は流動人口が多く、認知を広げやすい反面、競合も多くなりがちです。そのため、短時間授業のコマ割りや、夜遅くまで対応する時間設定など、忙しい生徒や保護者のニーズに合わせた柔軟な運営がカギです。実際に、駅から徒歩1分の立地に出店した塾では、ビル1階に看板を設置し、通行人への訴求力を高める工夫を取り入れ、開業半年で定員の7割を達成しました。
住宅街・郊外型:地域密着で勝つ運営方針
住宅街や郊外での塾運営では、地域に根差した信頼構築が成功のポイントです。学校のスケジュールに合わせた授業設定や、定期的な保護者面談を通じて「面倒見の良さ」を訴求するスタイルが効果的です。実例として、郊外に開校した個人塾が地域イベントに協賛し、地域住民との接点を持ったことで、口コミ中心に生徒数が伸びた事例があります。チラシよりも“近所の信頼”がものを言う地域です。
学校近くの塾:需要の波を見越した戦略とは
学校に近い塾は、試験前や学期末など「需要の波」が明確な点が特徴です。たとえば定期テスト前には自習室を無料開放する、模試の返却タイミングに合わせて個別面談を行うなど、学校行事と連動したサービス設計が効果的です。また、同じ学校に通う生徒が多いため、指導内容や進度を標準化しやすいというメリットも。学習ニーズの増減を見越した柔軟な対応力が求められます。
立地選定で迷ったときの判断軸と相談先

物件選びに迷ったときは、感覚ではなく「数字」と「専門家」の視点を取り入れることで、より確実な意思決定ができます。
最終判断は「生徒数×坪単価×競合数」の視点
収益性を数値で判断するには、「想定生徒数×月謝」が家賃などの固定費を上回るかが基本軸です。たとえば、月謝2万円で30名見込める場合、月収入は60万円。ここから家賃・人件費・広告費を引いて黒字化できるかをシミュレーションしましょう。また、周辺の競合数が多い場合は、単価設定や差別化の戦略も必要。坪単価が高くても「生徒を集められるか」を冷静に分析することが大切です。
物件選定で活用できるツール・不動産業者
エリア相場や周辺環境を把握するには、商圏分析ツール(例:タウンページデータ、RESAS)や地図アプリの活用が有効です。駅からの距離や競合との分布も可視化できます。また、塾や医療など特定業種に強い不動産業者に相談することで、ニーズに合った物件が見つかりやすくなります。実際に過去の塾開業支援実績がある不動産会社を選ぶのがポイントです。
フランチャイズ本部や開業支援者の知見を活かす
フランチャイズに加盟する場合は、本部から物件選定や立地診断のサポートを受けられるケースが多くあります。実績データに基づいたシミュレーションや、類似立地での成功・失敗事例の共有など、個人では得られない知見が得られるのが大きなメリットです。また、開業コンサルタントや創業支援事業者と連携することで、契約や資金面のアドバイスも得られ、より安心して立地選定が行えます。
まとめ
塾の立地選びは、単に家賃や人通りだけで判断するものではありません。ターゲット層・競合環境・周辺の利便性などを多角的に分析することで、長く安定した経営が可能になります。焦らず、現地確認や専門家の意見も活かしながら、確実な一歩を踏み出しましょう。

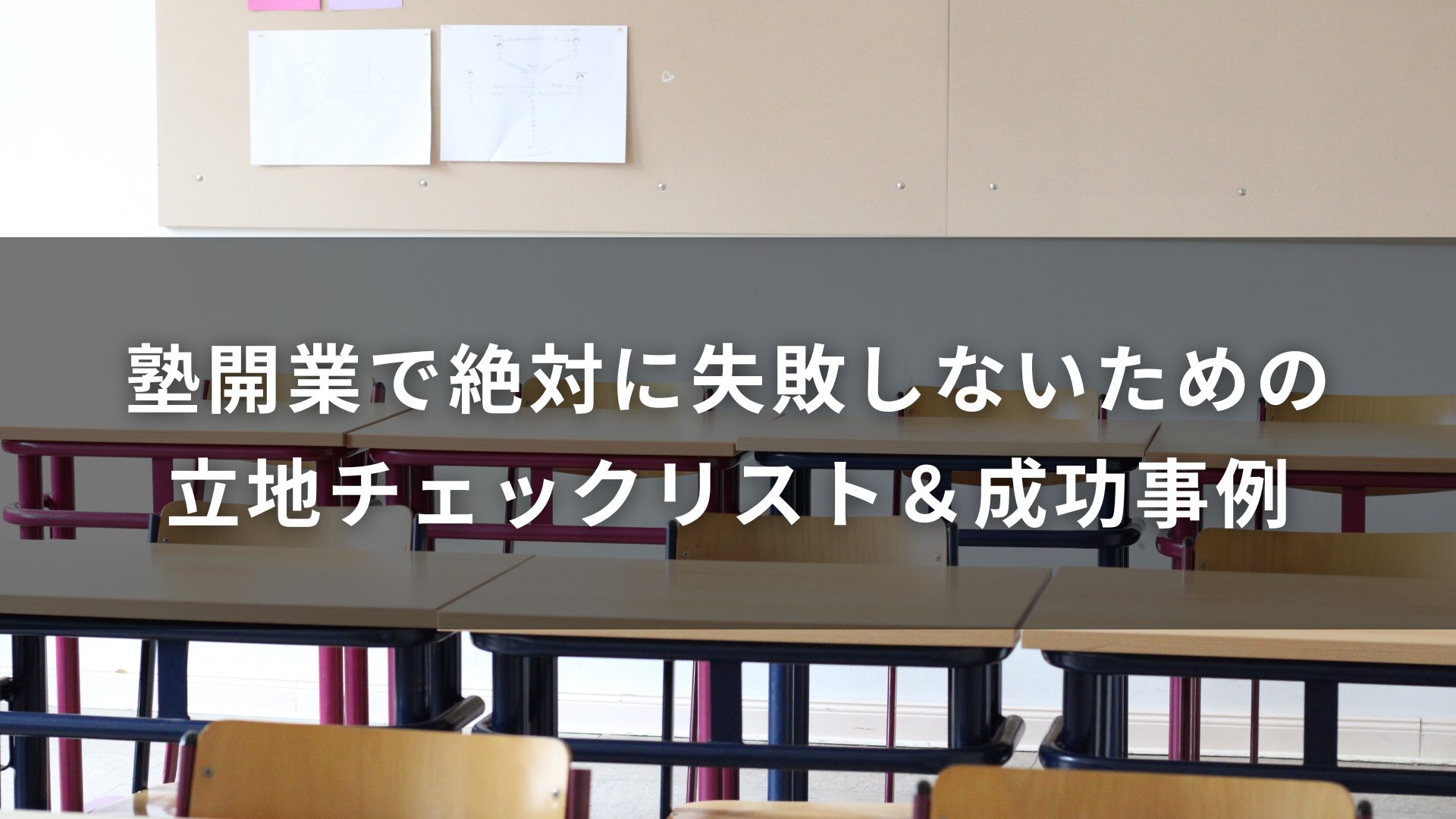
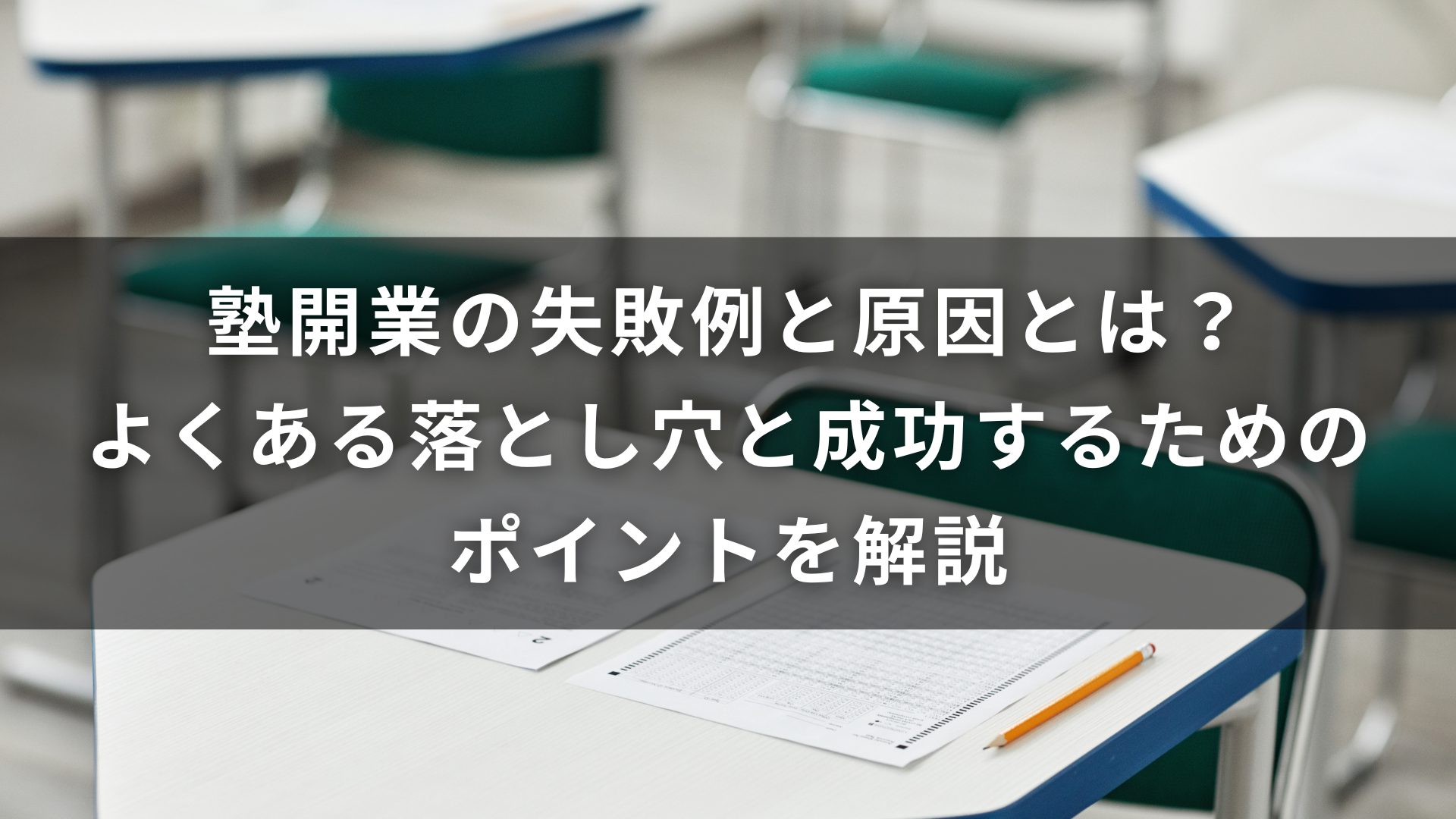
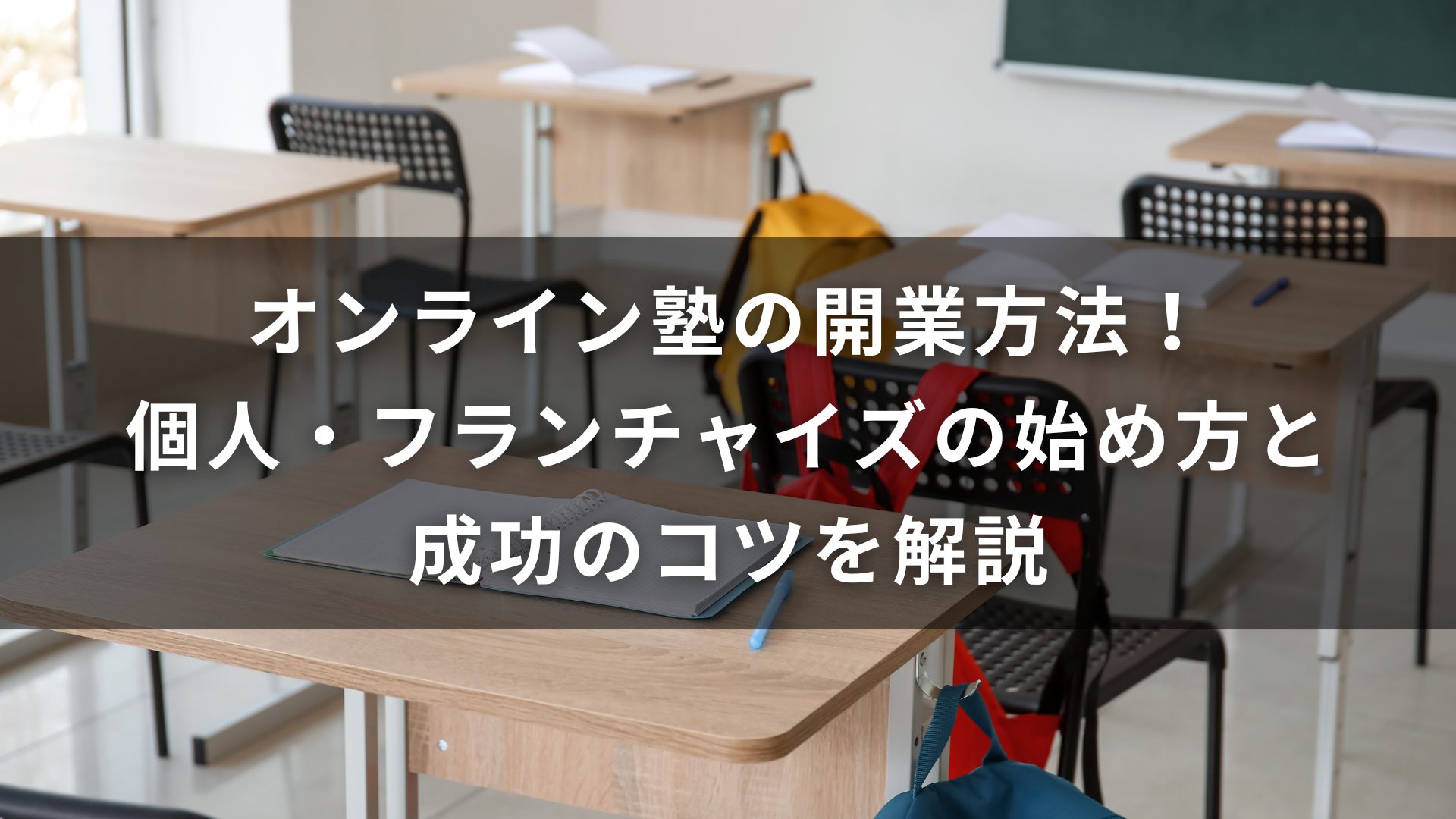
コメント