「オンライン塾を開業したいけど、何から始めればいい?」そんな悩みを持つ方に向けて、この記事ではオンライン塾の開業方法をわかりやすく解説します。必要な準備・費用・手続き・集客方法から、開業後によくある失敗とその対策まで、成功のためのポイントを網羅的にご紹介します。
オンライン塾の開業とは?まずは全体像を把握しよう

オンライン塾を始める前に、まずはその特徴やメリット・デメリットなど、基本的な全体像を押さえておきましょう。
オンライン塾の特徴とメリット
オンライン塾とは、パソコンやスマートフォンなどを通じて、インターネット上で授業を行う塾のことです。対面型の塾と違って教室を構える必要がなく、自宅などどこでも開業できるのが最大の特徴です。初期費用や家賃がかからず、全国どこからでも生徒を募集できるため、低リスクで高い柔軟性をもつビジネスとして注目を集めています。講師の働き方も自由度が高く、スケジュールや教材も柔軟に設計可能です。
オンライン塾の注意点・デメリット
一方で、インターネット環境に依存するため、通信トラブルや操作の不慣れが授業の妨げになることも。また、生徒との距離が画面越しになるため、関係性を築くには工夫が必要です。さらに、自宅開業が多いため、自己管理力や信頼構築、クレーム対応など、講師に求められるスキルも広範囲になります。これらを踏まえた上で、準備と運営体制を整えることが成功の鍵です。
開業までの流れ
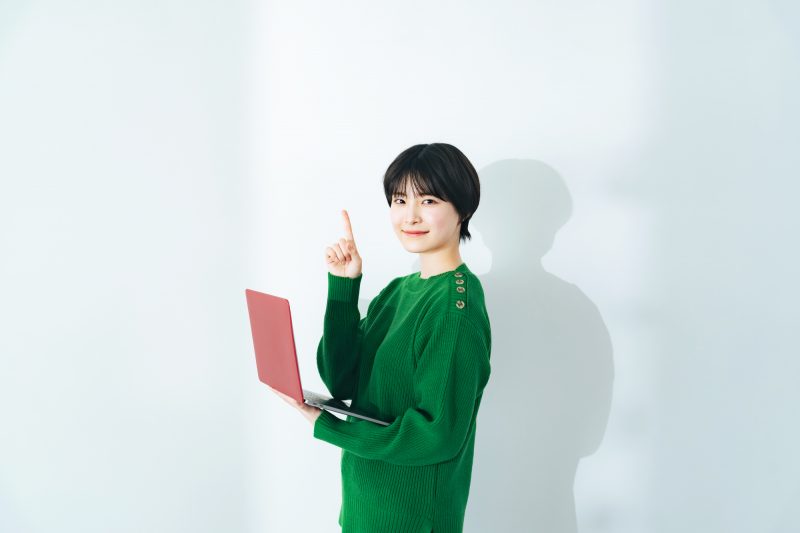
開業を決意したら、次は準備のステップです。ここではオンライン塾を始めるまでに必要な準備の流れを具体的に解説します。
ターゲット設定・授業内容の決定
まず最初に取り組むべきは、「どんな生徒に」「どんな指導をするか」を明確にすることです。対象は小学生か中高生か、受験指導か補習か、マンツーマンか集団かなど、授業の方向性を決めましょう。この段階でターゲットを絞っておくことで、教材や集客の方法もブレずに決めやすくなります。
カリキュラム・教材の準備
授業の方針が決まったら、それに沿った教材やカリキュラムを準備します。市販の教材を使う方法もありますが、自作する場合はデジタル化を意識しておくと便利です。動画・PDF・スライドなど、オンラインで扱いやすい形式で整えておくと、授業の進行がスムーズになります。
ツール・機材の準備
オンライン塾では、通信環境や機材のクオリティが授業の質に直結します。パソコンやマイク、ウェブカメラなどは性能の良いものを選びましょう。また、ZoomやGoogle Meet、Skypeなどの授業用ツールの使い勝手も事前に確認しておくと安心です。
開業届などの手続き(個人事業主登録)
オンラインであっても、塾を自ら運営して収益を得る場合は「事業」とみなされるため、税務署への「開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)」の提出が必要です。
開業届を出すことで、個人事業主として正式に登録され、青色申告を選択すれば節税効果や記帳面でのメリットも得られます。
また、屋号(塾名)付きの銀行口座を開設できる、経費処理がしやすくなる、信用度が高まるなど、事業運営上のメリットも大きいため、オンライン塾でも開業時には忘れずに提出しましょう。
開業届の提出はマイナンバーカードとe‑Tax(イータックス)を使えば、PCまたはスマホから場所・時間を問わず24時間手続きが可能です。
集客の準備(Webサイト・SNS・広告)
授業の準備が整ったら、生徒を集めるための準備を始めます。自作のWebサイトやブログを立ち上げるほか、X(旧Twitter)やInstagramなどのSNSを使った情報発信も効果的です。また、Google広告やLINE広告などを活用することで、認知度を高めることも可能です。
初回授業スタート!運営しながら改善していく
いよいよ初回授業です。始めは緊張するかもしれませんが、実施後のフィードバックをもとに、授業内容や進行方法を少しずつ改善していくことが成功のカギです。
オンライン塾では、ZoomやGoogle Meetなどのツールを活用した配信の安定性や操作のしやすさも重要なポイントになります。
また、授業の質だけでなく、生徒や保護者とのチャットやメールでのこまめなフォロー、アンケート機能などを活用した満足度の把握も意識しながら運営していきましょう。
オンライン塾開業にかかる費用・必要資金

オンライン塾の開業には、どの程度の費用がかかるのでしょうか?個人で始める場合とフランチャイズに加盟する場合に分けて見ていきましょう。
個人開業の場合
個人でオンライン塾を開業する場合、教室を借りる必要がないため初期費用は比較的低く抑えられます。主な出費は以下のとおりです。
①パソコンやウェブカメラ、マイクなどの機材購入(5万〜15万円程度)
②オンライン授業ツール(Zoomなど)の有料プラン(無料〜数千円/月)
③Webサイトやロゴ作成などの初期整備(自作なら無料〜、外注なら数万円)
④広告・集客費(月1〜3万円程度)
全体としては、10万円〜30万円程度でスタートできるケースが多く、自宅を活用すれば家賃も不要です。
フランチャイズの場合
フランチャイズに加盟する場合は、個人開業に比べて費用が高くなりますが、その分ノウハウやブランド力を活用できるメリットがあります。主な内訳は以下の通りです。
①加盟金(20万円〜100万円以上 ※フランチャイズ本部によって差が大きい)
②ロイヤリティ(月額制または売上の一定割合)
③システム利用料、教材費、サポート費用など(別途発生)
初期費用の目安としては、50万円〜150万円程度を見込んでおくと安心です。本部が集客・教材・研修を一括提供してくれる場合、運営の負担は軽減されますが、収益の一部をロイヤリティとして支払う必要があります。
オンライン塾を開業するための手続きと法律面の確認
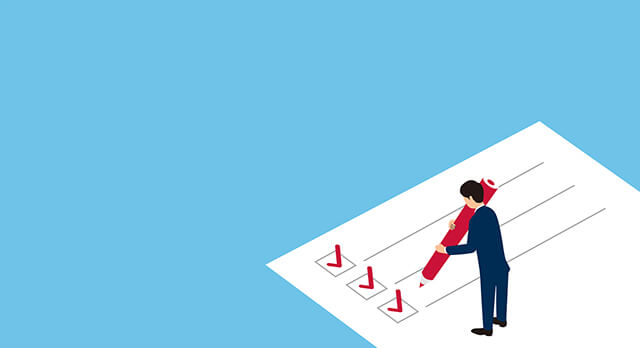
トラブルや違法運営を防ぐためにも、必要な手続きや法律面の対応を理解しておくことは非常に重要です。ここでは最低限押さえておきたいポイントを解説します。
開業届と個人事業主登録の流れ
オンライン塾を開業する際、まず行うべき基本手続きが「開業届」の提出です。これは、事業を開始することを税務署に届け出るための書類で、開業から1ヶ月以内の提出が原則です。これにより正式な「個人事業主」として認められます。
同時に「青色申告承認申請書」も提出しておくことで、最大65万円の特別控除をはじめとした節税メリットを受けることができます。屋号(ビジネス名)も開業届に記載でき、専用の銀行口座開設などにも活用できます。
必要に応じた届出(商標登録、通信教育事業の届け出など)
通常、オンライン塾の開業にあたって特別な許可は不要ですが、以下のようなケースでは追加手続きが必要になることがあります。
- ・名称(屋号・ブランド)を保護したい場合
商標登録を行うことで、他者による名称の無断使用を防止できます。将来的に事業を拡大する予定があるなら、早めの登録がおすすめです。 - ・教材を販売する場合
独自教材を販売する場合は、通信販売に関する表示義務(特定商取引法)を守る必要があります。 - ・学生や未成年を対象にする場合
自治体によっては青少年保護条例の対象になることもあるため、該当する場合は地域のルールを確認しておきましょう。
特定商取引法・個人情報保護法への対応
オンライン塾では、保護者との契約や個人情報の取り扱いが発生するため、以下の法律への対応が求められます。
- ・特定商取引法
受講料の返金ポリシーや、連絡先・運営者情報の明記など、サイトや契約時に必要な表示項目があります。これを怠ると行政指導の対象になる可能性があります。 - ・個人情報保護法
生徒の氏名・連絡先・成績などの情報を扱うため、適切な管理・利用目的の明示が必要です。プライバシーポリシーの掲載は必須と考えておきましょう。
生徒を集めるための集客・マーケティング戦略

どれだけ良い授業を用意しても、生徒が集まらなければ塾は成り立ちません。オンラインならではの集客手法と、効果的なマーケティングのポイントを紹介します。
SNSやブログでの情報発信
オンライン塾の集客では、SNSやブログなどによる情報発信が非常に効果的です。X(旧Twitter)やInstagramでは、保護者や学生に向けて塾の雰囲気や勉強のコツを日常的に発信することで、信頼感や親近感を育てることができます。
ブログでは、教育ノウハウや成績アップ事例などのコンテンツを投稿することで、SEO効果も期待できます。「中学生 数学 勉強法」など検索されやすいキーワードを狙うと効果的です。
広告(Google広告・Instagram広告など)の活用
短期間で成果を出したい場合は、広告の活用もおすすめです。Google広告では、「オンライン塾+地域名」などの検索連動型広告を出すことで、塾を探しているユーザーに直接アプローチできます。
また、InstagramやFacebookなどのSNS広告は、ターゲットとなる保護者層の興味関心や行動履歴に基づいた配信が可能。少額からスタートできるため、費用対効果を見ながら調整しやすいのもメリットです。
口コミや紹介で広げる仕組み作り
オンライン塾でも、口コミは強力な集客手段です。特に教育は「信頼」が重要なジャンルであり、「〇〇さんのお子さんが通っている塾」と聞くだけで、安心感が生まれます。
紹介制度を導入したり、保護者との面談やLINE配信でのコミュニケーションを丁寧に行うことで、自然と信頼が口コミへとつながります。“紹介したくなる”サービス品質と対応力を意識することが大切です。
無料体験授業の設計と反応を高めるポイント
「とりあえず一度試してみたい」というニーズに応えるのが、無料体験授業です。導入として非常に有効ですが、ただ実施するだけでは効果は薄く、“その後の入会につなげる設計”がカギとなります。
- ・授業内容は短くシンプルに(30分程度)
- ・保護者にも同席してもらい安心感を伝える
- ・体験後にフィードバック+特典(入会金無料など)を用意する
このように体験授業を「入会のきっかけ」にすることで、スムーズに次のアクションへつなげられます。
オンライン塾開業でよくある失敗と対策

開業後につまずきやすいポイントを事前に知っておくことで、トラブルや後悔を防ぐことができます。ここでは実際によくある失敗例とその対処法を解説します。
価格設定や内容のミスマッチによる失敗例
よくある失敗のひとつが、「価格とサービス内容が釣り合っていない」ケースです。
たとえば、高額な料金を設定しているにもかかわらず、教材やサポート体制が乏しい場合、保護者や生徒の満足度は低くなり、継続率も下がってしまいます。
特にオンライン塾では、対面でのやり取りがない分、「通塾の手間がない」という利便性以上に、どれだけ質の高いコンテンツやフォローを提供できるかが問われます。
オフライン塾に比べて「施設利用」や「直接指導」の価値を打ち出しにくいため、その分、料金設定にはより慎重さが求められます。
対策としては、競合の料金相場や提供サービスをしっかりリサーチし、自塾ならではの強みとバランスをとること。さらに、初回特典や月謝割引、体験授業の導入などで「始めやすさ」を演出するのも効果的です。
信頼を築くために必要なポイント
オンライン塾は、顔が見えない分、信頼関係の構築に時間がかかります。生徒や保護者との距離が近い対面型と比べ、対応が事務的になりがちで、「フォローが足りない」「相談しづらい」と感じさせてしまうこともあります。
これを防ぐには、LINEやメールでの定期フォロー、保護者との面談機会の確保、進捗報告の共有などを意識的に取り入れることが重要です。信頼を積み重ねる姿勢が、継続的な通塾や口コミにつながります。
継続的に運営するためのマインドと工夫
オンライン塾開業の初期は、思うように生徒が集まらなかったり、時間管理がうまくいかなかったりと、戸惑う場面も少なくありません。その結果、途中でモチベーションを失ってしまうケースもあります。
大切なのは、“一気に成功を目指す”より“地道に改善を続ける”マインドです。小さく始めて、実績を積み重ねながら少しずつ拡大することを前提に計画を立てましょう。進捗を記録したり、小さな成功体験を自分で認識することも、長く続けるコツのひとつです。
まとめ
オンライン塾の開業は、教室を持たずに自宅でスタートできるため、他のビジネスに比べて初期費用やリスクが低く、個人でも始めやすいのが大きな魅力です。
フランチャイズを活用すれば、未経験者でもサポートを受けながらスムーズに開業できる一方、自由度や収益性を重視するなら個人開業という選択肢も有効です。開業前には、ターゲット設定・教材準備・法的手続き・集客戦略までしっかりと計画を立て、自分に合ったスタイルを選ぶことが成功の鍵になります。
この記事を通じて、あなたの「やってみたい」を「できる」に変える一歩を踏み出すお手伝いができたなら幸いです。

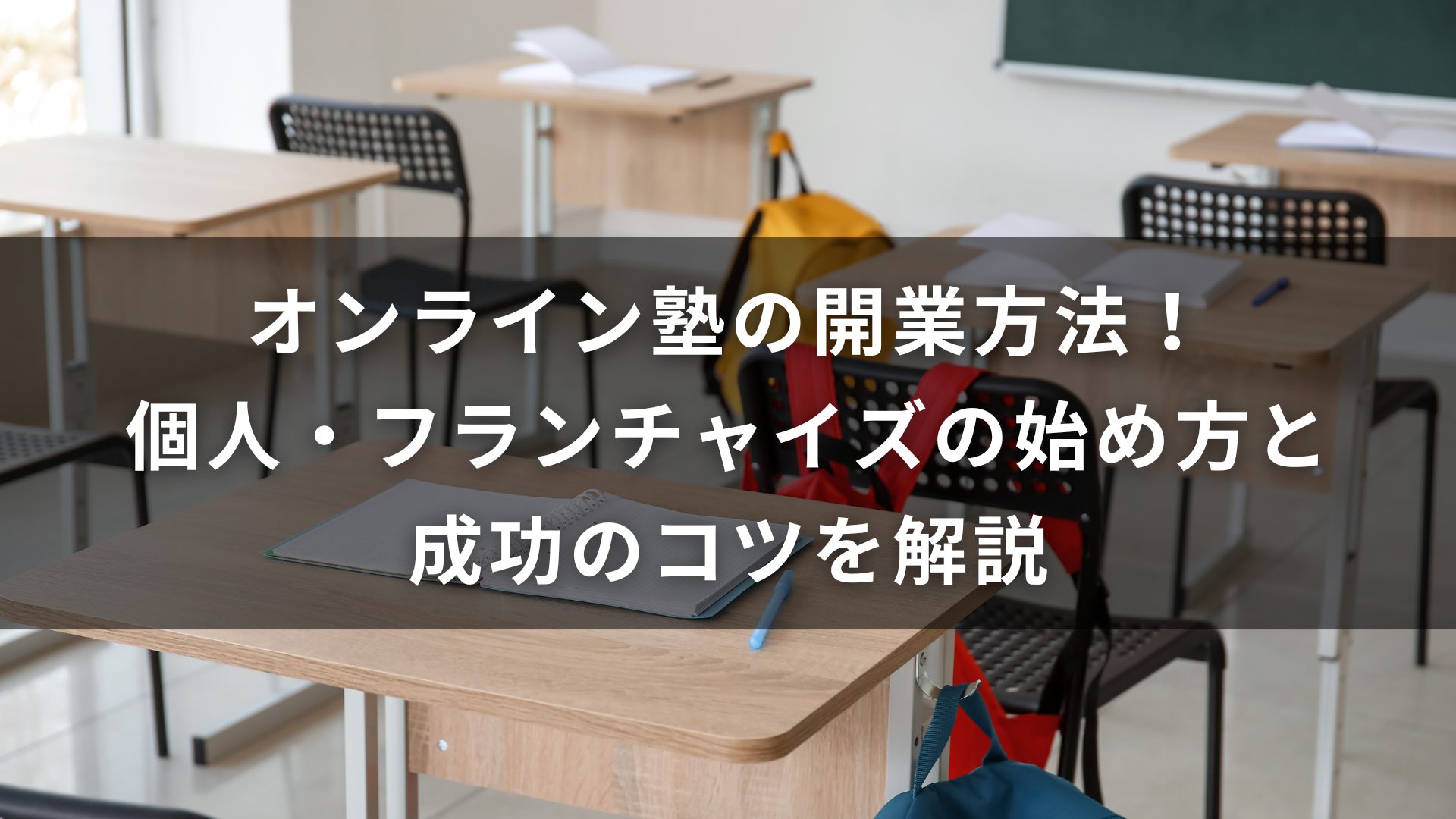
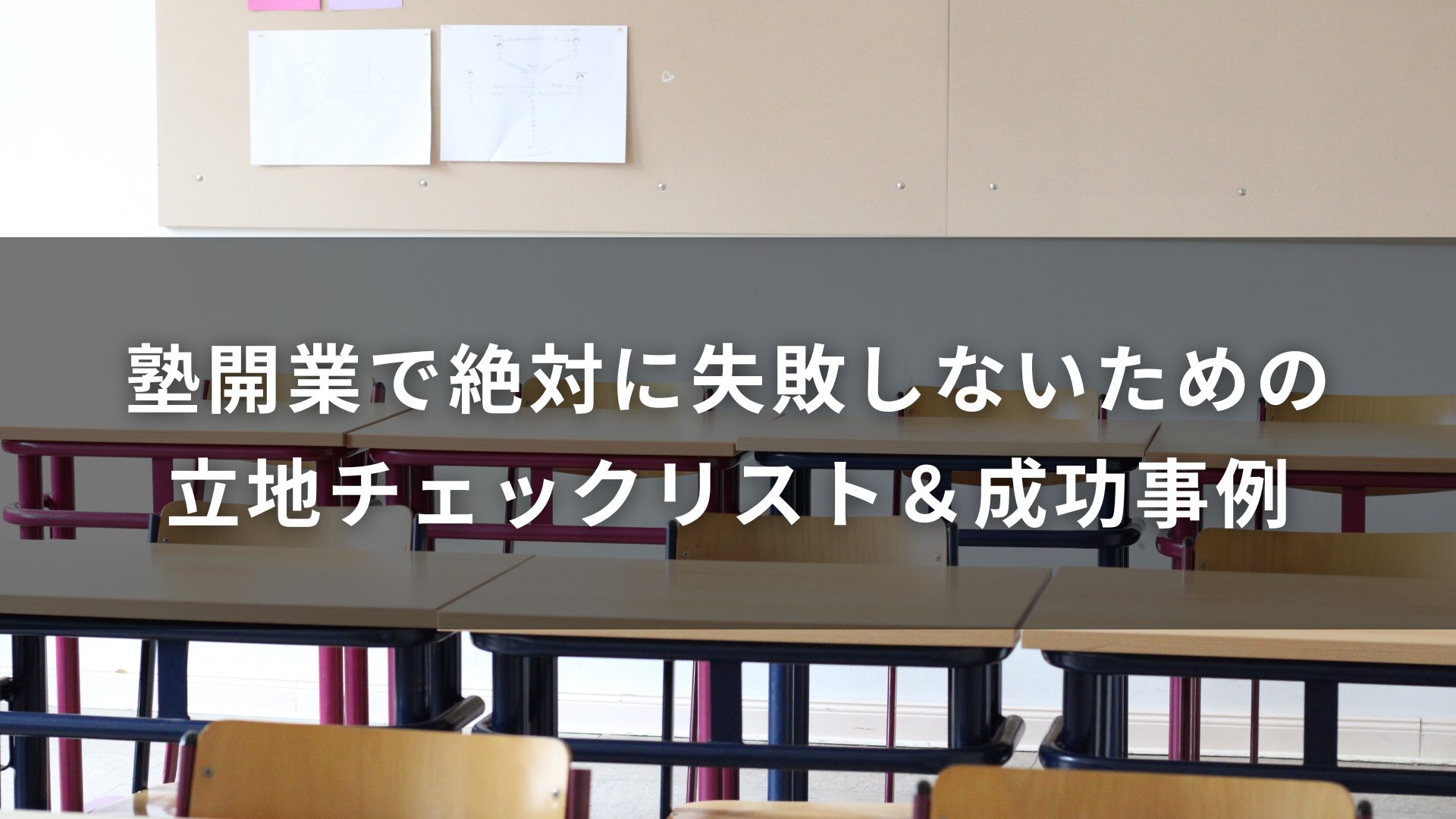
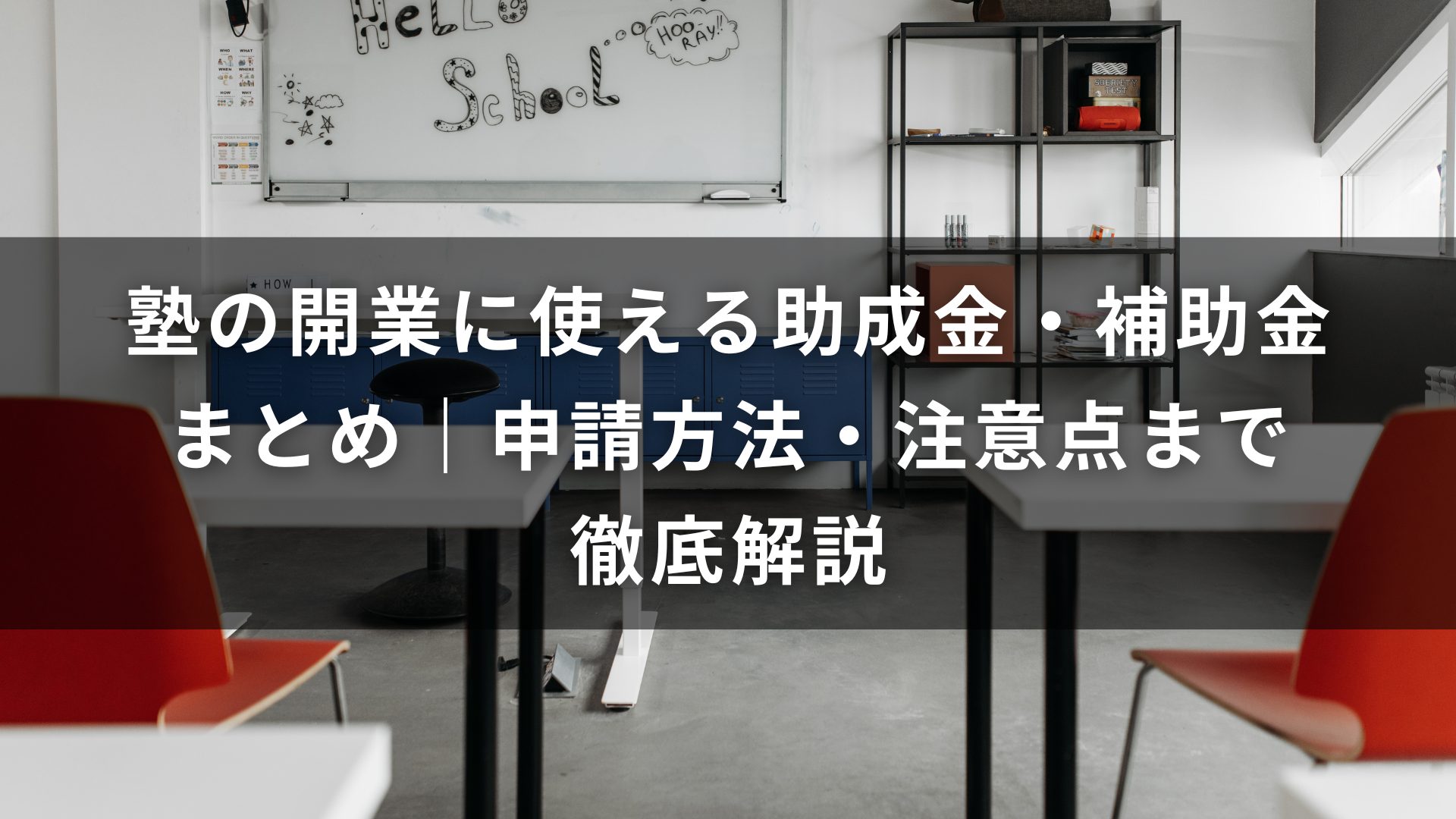
コメント