「塾を開業したいけど、資金面が不安…」そんな方にとって、助成金や補助金は大きな味方になります。
この記事では、塾の開業時に活用できる主な制度とその申請方法、注意点までをわかりやすく解説します。個人経営とフランチャイズの違いや、よくある疑問にも触れながら、あなたの開業をサポートする内容をまとめています。
塾の開業に助成金は使えるのか?

塾の開業には何かと費用がかかりますが、実は助成金や補助金を活用することで、初期コストを大きく抑えることができます。
ここでは、塾が助成制度の対象になるのか、制度の種類や違いについて整理して解説します。
塾の開業にかかる費用
学習塾の開業には、設備費・教材費・広告費・人件費など、さまざまな初期投資が必要です。
たとえば教室を構える場合、内装や備品の整備だけで数十万円〜数百万円がかかることもあります。さらにWebサイトや集客用のチラシ、広告出稿にも費用が発生します。オンライン塾であっても、通信環境や配信ツール、PC機材などの準備は不可欠です。
こうした出費をカバーする手段のひとつが、国や自治体による「助成金・補助金」です。
塾経営は助成金・補助金の対象になる?
塾のような教育サービスも条件を満たせば助成金や補助金の対象になります。
特に、地域活性化・雇用創出・IT化・創業支援といった目的を持つ制度では、塾経営も対象業種に含まれています。
ただし、全ての制度が自動的に適用されるわけではなく、対象となるには申請時の業態・雇用状況・地域条件などを満たす必要があります。
助成金と補助金の違いとは?
似たように見える「助成金」と「補助金」ですが、性質には明確な違いがあります。
| 種類 | 特徴 | 採択の有無 | 返済義務 |
| 助成金 | 主に厚生労働省系。条件を満たせば原則受給可。 | なし(審査はあるが採択制ではない) | なし |
| 補助金 | 経済産業省・中小企業庁系が多い。 | あり(競争的/審査制) | なし |
つまり、助成金は「条件クリア型」、補助金は「審査合格型」と理解しておくとよいでしょう。
助成金が受けられる主なケースとは?
以下のような状況であれば、助成金や補助金を受けられる可能性があります。
- ・地方で塾を開業し、地域雇用に貢献する(例:地域雇用開発助成金)
- ・新たに教育サービスを始める創業者(例:創業支援補助金)
- ・生徒管理やオンライン授業など、ITシステムを導入する(例:IT導入補助金)
- ・女性や若者、シニアなどの特定層の創業者(例:政策金融公庫の特別融資)
自分の開業スタイルや地域、目的に合った制度を選ぶことが、活用の第一歩です。
塾の開業時に活用できる代表的な助成金・補助金一覧
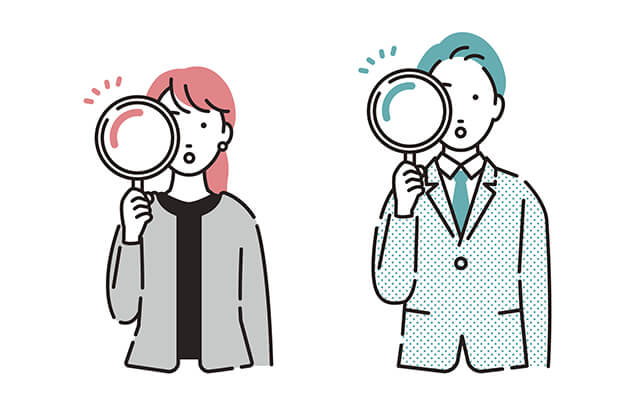
塾を開業する際に活用できる助成金・補助金は、国・自治体・公的機関など複数のルートから提供されています。ここでは、比較的多くの人が対象となりやすい代表的な制度を5つご紹介します。
地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)
この制度は、厚生労働省が実施する助成金で、地方(過疎地や雇用機会が少ない地域)に事業所を設置し、従業員を新たに雇用する場合に支給されます。
学習塾も対象事業に含まれており、要件を満たせば開業にかかる経費の一部が助成されます。
- ・対象:対象地域で事業所を開設し、ハローワーク経由で労働者を常用雇用
- ・助成額:最大で年間900万円(最大3年間)
- ・対象経費:施設整備、備品購入、広告費、人件費など
塾を開くと同時に地域雇用にも貢献できる場合は、非常に効果的な制度です。
日本政策金融公庫
助成金ではありませんが、創業時に有利な条件で資金を借りられる公的融資制度として、日本政策金融公庫は多くの塾開業者が活用しています。
特に、以下のような制度があります。
- ・新創業融資制度(無担保・無保証)
- ・女性・若者・シニア起業家支援資金(特別利率で融資)
- ・教育関連事業に特化した支援相談も可能
創業時に自己資金が十分でない場合でも、これらの制度を併用することで資金繰りを安定させやすくなります。
※参照:日本政策金融公庫
小規模事業者持続化補助金
中小企業庁が主催する補助金制度で、販路開拓や業務効率化のための費用を支援してくれます。
- ・補助率:対象経費の2/3
- ・上限額:通常枠は50万円(特例ありで100万円以上も)
- ・対象:チラシ制作、ホームページ作成、看板設置、設備投資など
塾の集客・ブランディング・設備導入を考えている方には非常に使いやすい制度です。
ただし、採択制であり、提出書類の質が重要になります。
※参照:小規模事業者持続化補助金
創業支援等事業者補助金(自治体による)
こちらは、市区町村が独自に実施する創業支援制度で、地域内の創業者に対して補助金や支援を行うものです。
- ・内容例:賃料補助、開業費用の一部補助、事業計画サポートなど
- ・補助額:最大50万円〜200万円程度(地域によって異なる)
- ・申請条件:開業後半年以内/商工会議所の創業支援プログラム修了など
地域によって内容は異なりますが、自分が開業する市町村で必ず確認しておくべき制度のひとつです。
※参照:創業助成金(東京都中小企業振興公社)|融資・助成制度
IT導入補助金
IT導入補助金は、業務効率化や生産性向上を目的にITツールを導入する企業・個人事業主向けの制度です。オンライン塾を想定した設備導入にも活用可能です。
- ・対象経費:生徒管理システム、予約ツール、LMS(学習管理システム)など
- ・補助率:1/2~3/4(導入内容により変動)
- ・上限額:通常枠で最大450万円程度
注意点として、事前に「IT導入支援事業者」と連携して申請する必要があるため、早めの準備が必要です。
助成金を活用した塾開業の進め方

助成金・補助金は魅力的な制度ですが、申請には計画性と準備が必要です。ここでは、塾の開業を成功させるために、助成金を活用する上で重要なステップを紹介します。
助成金獲得のための開業計画の立て方
助成金の多くは、「誰にどんなサービスを提供するか」「なぜその事業が必要なのか」といった事業の目的や社会的意義が明確になっていることを重視します。
塾の場合は、次のような観点から開業計画を考えるとよいでしょう。
- ・対象となる生徒層(小学生・中学生・高校生 など)
- ・教育課題や地域ニーズ(例:地域に塾が少ない、補習ニーズがある など)
- ・授業の特長や差別化ポイント(例:個別指導・オンライン対応・発達支援など)
- ・数年後までの運営方針と見通し(売上見込み、生徒数推移など)
このように、“支援する価値がある事業”と感じてもらえるストーリー設計がカギになります。
事業計画書に盛り込むべきポイント
補助金申請の審査では、提出する「事業計画書」の内容が採否を左右します。
以下のポイントを押さえて作成しましょう。
- ・課題の明確化と事業の必要性
例:「地域の学力格差を埋めるため」「家庭教師が高額で手が届かない家庭に」など - ・事業の独自性や革新性
例:「オンラインと対面を組み合わせたハイブリッド型指導」など - ・具体的な収支計画と効果予測
例:初年度は生徒数〇名を目標に、売上〇円/月を見込む など - ・補助金の使い道と効果
例:「教材費・広告費・HP制作費に充てることで、生徒募集を強化」など
これらを盛り込むことで、審査担当者に伝わりやすく、採択される可能性が高まります。
専門家(商工会・税理士など)に相談するメリット
補助金や助成金の申請は、制度ごとに書類形式・審査観点・スケジュールが異なり、初めての方にとっては非常に複雑です。そんなときは、以下のような専門機関を頼るとスムーズに進みます。
- ・商工会・商工会議所:申請書類の添削や制度選びのアドバイスを無料で提供
- ・認定支援機関:持続化補助金などの一部制度では、申請において関与が必須
- ・税理士・行政書士:事業計画の整合性や数値面のサポート、申請代行も可能(有料)
専門家の支援を受けることで、手続きミスや不採択リスクを大きく減らすことができ、安心して開業準備を進められます。
助成金申請の手続きと流れ

助成金や補助金を活用するには、計画的な準備と申請手続きが必要です。この章では、申請から受給までの基本的な流れを3つのステップに分けて解説します。
公募時期と申請期限のチェック
補助金や助成金は、通年で募集しているわけではありません。
特に補助金は「公募期間」が決まっており、申請期限を過ぎると応募すらできなくなるので注意が必要です。
- ・補助金(例:持続化補助金)は年に2〜5回程度の公募がある
- ・助成金(例:雇用系)は比較的常時受け付けているが、予算枠が尽きると終了することも
- ・地方自治体の補助金は、年度内で予算消化されるケースも多い
最新情報は、制度の公式サイトや商工会議所・自治体のHPでこまめにチェックしましょう。
必要書類と提出方法
申請には、制度ごとに求められる複数の書類を正しく揃える必要があります。
代表的な提出書類は以下の通りです。
- ・事業計画書(補助金の使い道・効果を明記)
- ・開業予定地の図面・契約書類(賃貸契約書など)
- ・見積書(設備や広告にかかる費用の根拠)
- ・本人確認書類、開業届(または予定証明)
提出方法は、郵送・持参・オンライン申請(jGrantsなど)など制度ごとに異なるため、必ず要領を確認しましょう。
審査・採択後の流れと注意点
申請が完了すると、補助金の場合は「審査」→「採択通知」→「事業実施」→「報告・精算」という流れになります。
- ・審査結果の通知は1〜2ヶ月後が目安(制度により異なる)
- ・採択後に事業を開始する必要がある場合が多いため、採択前に経費を使うと対象外になることも
- ・補助金は事業終了後に「実績報告書+領収書等の証拠書類」を提出し、精算・入金される
このように、補助金は後払い方式(事後精算)が基本なので、一時的に自己資金で立て替える準備が必要です。
よくある疑問と注意点

助成金や補助金を調べると、「本当に使えるのか?」「もし落ちたらどうなる?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。ここでは、塾の開業に関連するよくある質問と注意点を解説します。
開業後でも助成金はもらえる?
制度によって「開業前」の申請が必須のものと、「開業後」でも申請可能なものがあります。
- ・補助金(例:持続化補助金)…原則、採択される前に経費を使うと対象外になるため、「開業前」に申請が必要
- ・助成金(例:地域雇用開発助成金)…開業後でも一定期間内であれば申請可能なケースあり
そのため、「開業時に使いたい」と思っている助成金がある場合は、開業日をずらしてでも事前に制度を確認・申請準備を進めるべきです。
複数の助成金を併用できる?
基本的には、制度が重複しなければ併用は可能です。
たとえば、以下のような組み合わせが一般的に認められています。
- ・小規模事業者持続化補助金(集客費用など)+ 日本政策金融公庫(開業資金の融資)
- ・IT導入補助金(システム導入)+ 地域雇用開発助成金(雇用拡大)
ただし、同一の経費に対して複数制度を重ねて申請することはできません(いわゆる“二重取り”の禁止)。申請する際は、各制度の対象経費を明確に分けることがポイントです。
不採択だった場合の対処法
補助金は競争的な制度が多く、申請しても不採択になることは珍しくありません。
しかし、落ちた場合も次のような方法で対応が可能です。
- ・申請内容をブラッシュアップして次回の公募で再チャレンジする
- ・別の補助金制度に切り替えて申請する(内容に合った制度を探す)
- ・自己資金や融資に切り替えて開業スケジュールを調整する
また、不採択の理由が明示されることもあるため、事業計画の改善材料として前向きに活用することが重要です。
まとめ
塾の開業には、設備や教材、広告費など多くの初期投資が必要です。しかし、助成金や補助金を上手に活用すれば、その負担を大きく軽減することが可能です。
国や自治体には、創業支援・IT化・地域雇用促進などさまざまな目的に応じた制度が用意されており、塾のような教育サービスでも条件を満たせば対象となります。
また、個人開業・フランチャイズいずれの形態でも利用できる制度はありますが、それぞれで注意点が異なるため、開業前にしっかり制度内容を確認し、計画的に準備を進めることが大切です。本記事で紹介した制度や流れを参考に、自分に合った支援を見つけて、助成金を味方にしたスムーズな塾開業を目指しましょう。

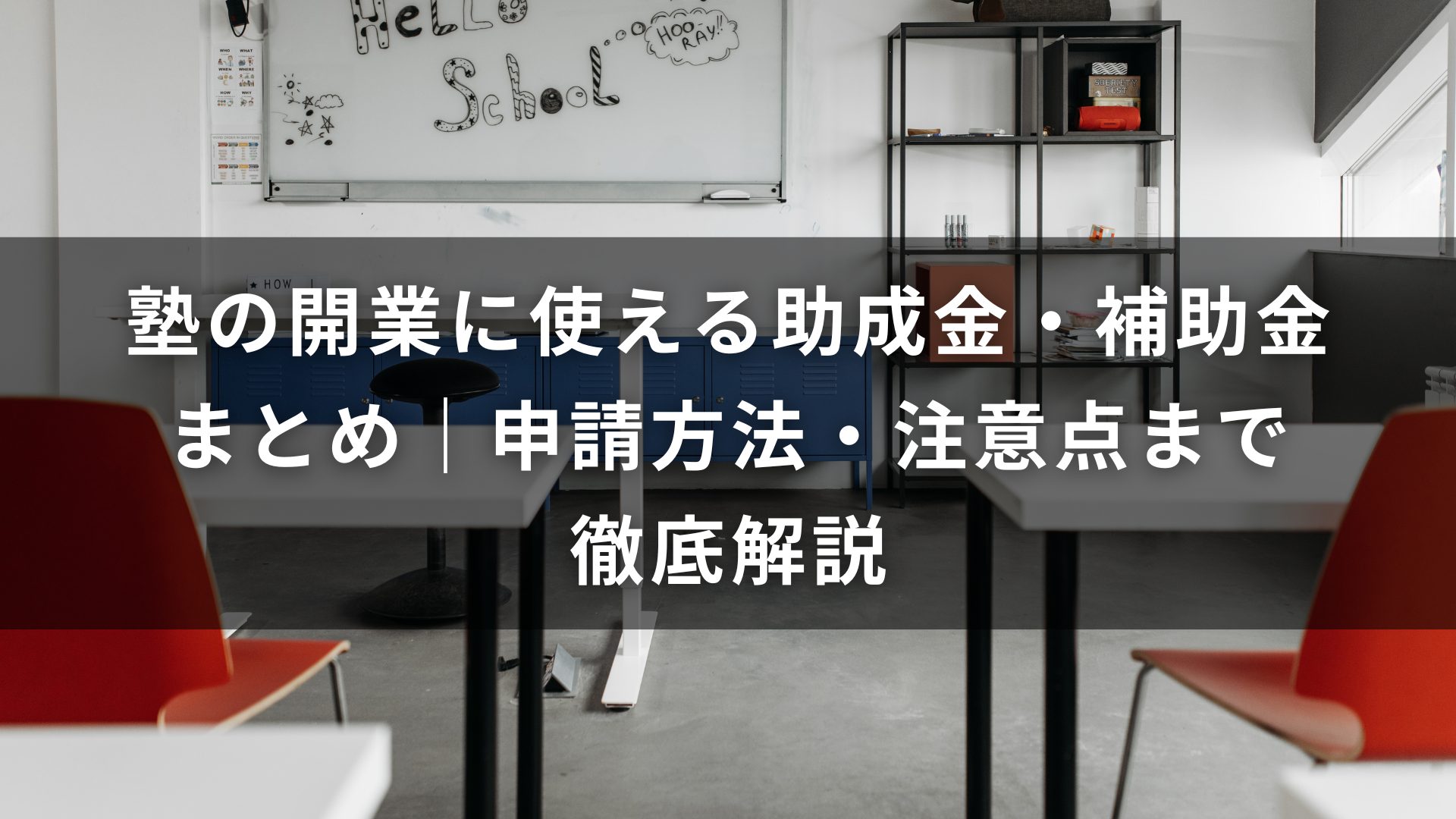
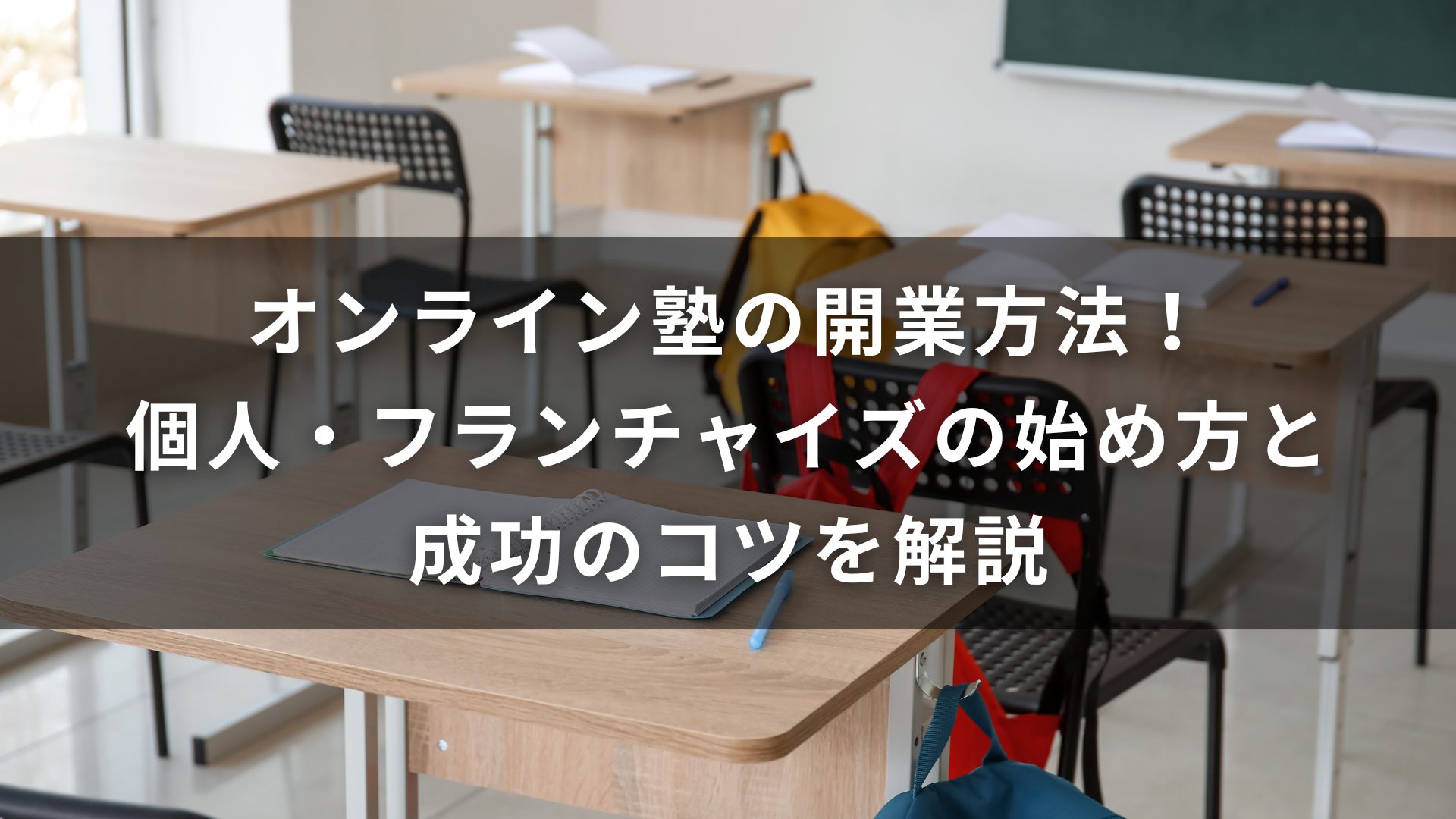
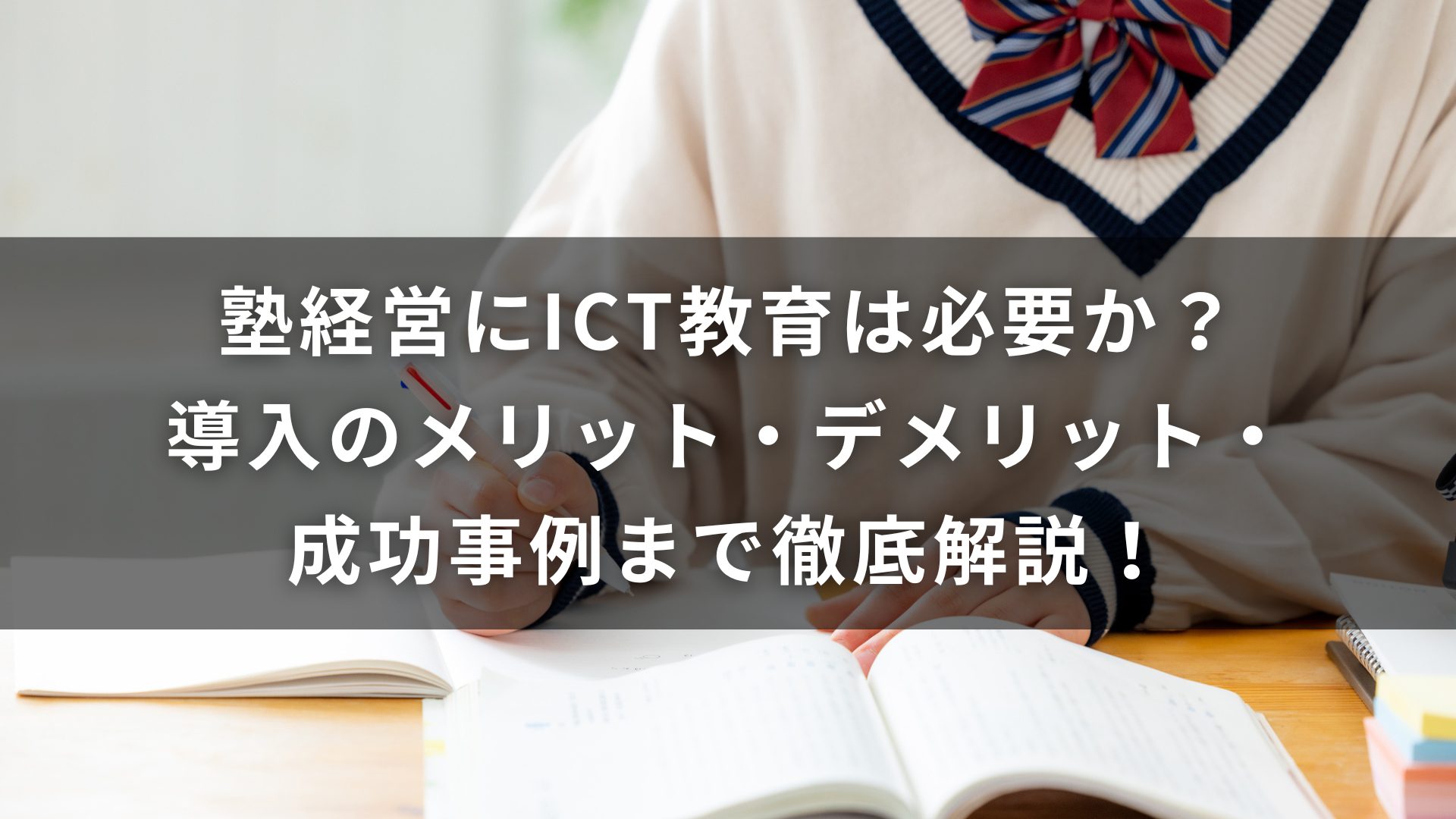
コメント