個人で塾を経営したいと考える人は増えていますが、「資金はどのくらい必要?」「資格は必要?」「生徒は集まるのか?」といった不安を抱える方も多いのが現実です。この記事では、開業に必要な準備から、成功するためのポイント、実際の体験談までをわかりやすく解説します。
個人で塾を経営するメリット・デメリット

個人で塾を経営する魅力は大きいですが、当然ながらリスクも存在します。自由度ややりがいといったポジティブな側面だけでなく、収入や時間、責任にまつわる現実も踏まえて、自分に向いているかを見極めることが重要です。
個人経営ならではの自由度と裁量
個人で塾を経営する最大のメリットは、自由度の高さにあります。授業スタイルや使用教材、開校時間、授業料などをすべて自分で決められるため、自分の理想とする教育をそのまま形にできます。特に、教員経験者や「自分の教育方針を貫きたい」という強い信念を持つ人には向いているスタイルです。また、大手塾にありがちな方針や制約に縛られず、生徒一人ひとりと密に関われる点も魅力。教育に対するこだわりや独自性を活かしたい人にとって、個人経営は大きなやりがいを感じられる働き方です。
収入面・時間面のリスクとは?
一方で、個人経営にはリスクも存在します。開業初期は生徒が少なく、収入がゼロの状態が数ヶ月続くケースも珍しくありません。経営が軌道に乗るまでは、広告費や設備投資などの出費が先行し、経済的な不安定さがつきまとうでしょう。また、営業、授業、保護者対応、経理などすべての業務を1人でこなす必要があるため、時間的拘束も大きくなります。体調管理やワークライフバランスにも注意が必要です。こうした現実を踏まえ、開業前には十分な資金の確保や、生活費の目処を立てておくことが大切です。熱意だけで突っ走るのではなく、リスクも見据えた慎重な準備が成功の鍵となります。
法人化との違いは?どちらを選ぶべき?
塾を始める際は、「個人事業」と「法人(株式会社など)」のどちらの形態で開業するかを選ぶ必要があります。個人事業は開業手続きが簡単で費用も抑えられますが、節税面や信用力では法人に劣る点もあります。法人化すれば社会的信用が高まり、融資や取引の際にも有利に働くことが多いですが、その分設立手続きや税務申告は複雑になります。
| 比較項目 | 個人事業 | 法人(株式会社) |
| 開業手続き | 簡単(開業届のみ) | 複雑(登記が必要) |
| 設立コスト | ほぼ不要 | 約20万円〜 |
| 税務処理 | 青色申告が可能 | 法人税対応が必要 |
| 節税の自由度 | 限定的 | 節税しやすい |
| 信用・対外印象 | やや低い | 高い |
個人で気軽に始めたい、スモールスタートを望む方には「個人事業」が向いています。一方、事業拡大を見据えていたり、最初から信用を重視したい方は「法人化」を検討する価値があります。それぞれのライフスタイルや目標に合わせて選択しましょう。
塾を開業するために必要な準備とステップ

「塾を始めたい」と思ったとき、最初に何から手を付ければいいのか迷う方も多いでしょう。ここでは、資格・物件・資金・手続きの4つのステップに分けて、開業までの道のりをわかりやすく解説します。
必要な資格・許認可はある?
塾を開業するにあたって、特別な資格は基本的に必要ありません。学習指導は無資格でも可能であり、教員免許が必須というわけではないため、誰でも始めやすいビジネスといえます。ただし、場合によっては注意すべき届け出が必要になります。たとえば、塾で火気を使用する場合は消防署への届け出が必要となることがありますし、防火対象物使用開始届の提出を求められるケースもあります。また、マンションで開業する場合は、近隣住民への配慮や管理規約の確認も欠かせません。「無資格でOK」という安心感がある一方で、最低限の法令順守や安全面への配慮は必要です。
物件探しと立地の選び方
塾経営において、物件の立地は生徒の集まりやすさに直結する重要な要素です。住宅街では通塾しやすく、地域密着型の塾に向いています。駅近なら高校生など交通機関を使う生徒が通いやすく、幅広い年齢層を狙えます。また、小学校や中学校の近くに位置すれば、放課後にすぐ立ち寄れる利便性が魅力です。一方、自宅を使った開業も可能ですが、マンションの場合は管理規約で営業が制限されていることがあるため、事前確認が必須です。さらに、自宅開業では看板の設置可否や騒音問題にも注意が必要です。開業後にトラブルにならないよう、物件選定は「ターゲットの通いやすさ」「近隣環境」「ルールの確認」の3点を意識して行いましょう。
初期費用の目安と資金調達方法
塾を開業するには、物件取得費用のほか、内装工事費・教材費・広告費・備品購入費など、まとまった初期費用が必要になります。以下は一般的な初期費用の内訳例です。
| 費用項目 | 金額目安 |
| 物件取得費(保証金含む) | 30万~80万円 |
| 内装・備品 | 10万~30万円 |
| 広告・チラシ制作 | 5万~20万円 |
| 教材・印刷費 | 3万~10万円 |
| 合計 | 約50万~200万円 |
資金調達の手段としては、まず自己資金のほか、親族からの借入、または「日本政策金融公庫」の創業融資制度の活用が考えられます。金融公庫は創業者支援に積極的で、事業計画書をしっかり準備すれば無担保・無保証での融資も可能です。その他、自治体による開業支援補助金や、民間のクラウドファンディングなども選択肢に入ります。大切なのは、初期費用だけでなく開業後3〜6ヶ月分の運転資金も見込んで資金計画を立てることです。
開業手続きの流れ(開業届・青色申告など)
個人で塾を始める場合、まず「個人事業の開業届出書」を税務署に提出する必要があります。これは開業日から1ヶ月以内が目安とされており、提出することで正式に個人事業主として登録されます。あわせて「青色申告承認申請書」を提出しておけば、最大65万円の控除が受けられるため節税にも有利です。申請は無料で、いずれも税務署の窓口や郵送、e-Taxで提出可能です。開業後は、売上や経費を帳簿に記録し、確定申告を行う必要があります。帳簿の記録には、会計ソフトの活用や、専門家への相談も検討するとよいでしょう。税務処理を後回しにするとトラブルの原因にもなるため、開業当初から帳簿管理の習慣を身につけておくことが重要です。
塾経営にかかる費用と収益モデル

塾を開業した後、「月にいくらかかるのか」「どのくらい稼げるのか」は誰もが気になるポイントです。このセクションでは、運営にかかる費用の内訳と、収益のモデルケースをわかりやすく解説します。
月間のランニングコストの内訳
塾経営における月々の固定費は、教室の規模や運営スタイルによって大きく変わります。代表的なランニングコストは以下の通りです。
①家賃・共益費:5万~15万円(立地・規模による)
②光熱費・通信費:1万~2万円
③広告・Web費用:1万~3万円(Googleマップ・サイト維持など)
④教材・印刷費:5千~1万円
⑤人件費(講師を雇用する場合):5万~20万円以上
最小構成で自宅開業・1人運営なら月5万〜8万円程度に抑えることも可能ですが、講師を雇って複数生徒を指導する体制を取る場合は、15万円〜30万円程度かかることもあります。費用を把握し、無理のない経営を心がけましょう。
月商のモデルケース
塾の月商(売上)は、「生徒数 × 月謝」で決まります。以下は1人で指導することを前提としたシミュレーション例です。
| 生徒数 | 月謝 | 月商合計 |
| 10人 | 1万円 | 10万円 |
| 20人 | 1万5千円 | 30万円 |
| 30人 | 1万円 | 30万円 |
実際には、生徒数が増えるほど指導時間も長くなり、対応できる人数には限界があります。たとえば1日2〜3時間、週5日稼働とした場合、現実的に対応できる生徒数は20〜25人程度が上限です。授業形態(個別/少人数/一斉指導)や料金体系の工夫によって、売上の上限をどう設計するかが経営の鍵になります。
損益分岐点はどこか?
損益分岐点とは、「売上=経費」となるラインのこと。つまり、黒字か赤字かの分かれ目です。以下のように、塾経営にかかる固定費と変動費を整理してみましょう。
| 費用項目 | 月額(目安) |
| 家賃・光熱費 | 7万円 |
| 広告・通信費 | 2万円 |
| 教材費 | 5千円 |
| 人件費(講師1人) | 10万円 |
| 合計(固定費) | 約19万5千円 |
この場合、月謝1万円なら生徒20人弱で損益分岐点に達します。生徒数がそれ以下だと赤字、超えれば黒字という計算です。ただし、広告や人件費を抑える、授業料を上げるなどの工夫で分岐点は下げられます。経費を毎月見直しながら、損益分岐点を把握して経営判断を行うことが、継続的な塾運営には不可欠です。
生徒集客の具体的な方法

塾の経営を軌道に乗せるためには、生徒を安定的に集めることが不可欠です。ここでは、地域密着型のオフライン施策から、デジタルを活用したオンライン施策まで、効果的な集客方法を具体的に紹介します。
近隣チラシ・ポスティングの効果的な使い方
地域密着型の塾にとって、チラシ配布は今もなお有効な集客手段です。効果を高めるには、ターゲットとなる小・中学校周辺の住宅地を狙うのがポイントです。ポスティングの時間帯は、保護者が郵便物をチェックしやすい夕方〜夜が効果的。デザインは、実績や指導内容がひと目でわかるように整理し、キャンペーン情報(入塾金無料など)を目立たせましょう。また、「子ども向け+保護者向け」の両方に訴求できる言葉選びも大切です。週末に地域のイベント会場や駅前などで配布するのも効果的な手段です。反応を見ながら配布エリアを調整し、PDCAを回すことが集客率アップの鍵になります。
塾検索サイト・Googleマップ・口コミ活用法
近年は、保護者がスマートフォンで塾を探すのが当たり前になってきています。そのため、「塾ナビ」「塾選」などの検索サイトへの登録は必須といえるでしょう。これらのサイトでは、地域や学年、対応教科などで絞り込んだ検索が可能なため、ニーズに合った生徒とマッチしやすくなります。また、Googleマップへのビジネス登録(Googleビジネスプロフィール)も重要です。写真・口コミ・営業時間などを掲載し、検索時に目に留まるよう最適化しましょう。口コミの集め方としては、入塾後の保護者に「よろしければ感想を投稿してください」とお願いするなど、無理のない範囲で依頼します。デジタル集客は継続運用がカギです。
学年別×ニーズ別のターゲティング例
塾の強みを生かすには、「誰に・何を教えるか」を明確にすることが大切です。以下のように、学年別×ニーズ別で具体的にメニューを打ち出すことで、保護者や生徒にとってわかりやすい訴求が可能になります。
①小学5年生 × 中学受験対策(中堅校狙い)
②中学1年生 × 英検3級対策(内申点アップ目的)
③中学3年生 × 都立高校の数学特化コース
④高校2年生 × 共通テスト数学対策コース
⑤高校3年生 × 総合型選抜の面接・小論文対策
こうした「誰の、どんな課題を解決できるか」が明確な塾は、他塾と差別化されやすく、集客効率も高くなります。SNS広告やGoogle広告を使ってピンポイントに訴求すれば、限られた予算でも効果を出しやすくなります。
塾経営を成功させるためのポイント

塾経営を軌道に乗せるためには、運営の仕組みだけでなく、集客や人材育成、保護者対応など“人”に関わる要素も重要です。ここでは、成功塾が実践している具体的なポイントを紹介します。
生徒が集まらない塾に共通する3つの失敗
個人塾で生徒が集まらない原因は、決して立地や価格だけではありません。共通して見られる失敗例には、以下のようなパターンがあります。
①チラシを配るだけで満足している
→反応率や配布エリアの分析をせず、改善が行われていない
②ターゲットが曖昧
→誰に何を提供する塾なのかが不明確で、保護者の選択肢に入らない
③料金・教科・学年がバラバラ
→統一感がなく、専門性や信頼感に欠けて見えてしまう
こうした問題を回避するには、ターゲット層と提供価値を明確にし、打ち出す情報に一貫性を持たせることが大切です。PDCAを回して施策を調整する「経営意識」が成果を分けます。
講師の確保・教育のコツ
講師の質は塾の評判と継続率を大きく左右します。個人塾では大学生アルバイトだけでなく、社会人の副業講師を活用するのも1つの方法です。大学の掲示板や求人媒体、スキルシェアサイトなどを活用して、教育に意欲のある人材を見つけましょう。採用後は、指導方法や教室の方針を丁寧に共有し、マニュアルや研修で質を均一化することが重要です。特に少人数で運営する個人塾では、経営者=現場責任者というケースも多いため、「自分がいなくても回る」仕組みを意識したマネジメントを整えることが、持続可能な経営につながります。
保護者との信頼関係が継続率を決める
塾経営において、生徒の成績向上と同じくらい大切なのが保護者との信頼構築です。問い合わせ後・体験後・入塾後と、各タイミングでの丁寧な対応が、継続率や口コミに大きな影響を与えます。たとえば、月1回の学習レポート提出や、LINEやメールでの連絡体制を整えることで、「子どもの状況を常に把握してくれている」と感じてもらいやすくなります。保護者の不安に寄り添い、こまめに情報共有を行うことで、信頼が積み重なり、長期在籍や紹介にもつながるのです。継続=経営の安定と考え、保護者対応を“戦略的に”行いましょう。
個人経営とフランチャイズの違い

塾を始める方法には、大きく分けて「完全個人経営」と「フランチャイズ加盟」の2パターンがあります。ここでは、それぞれの特徴や収益性、向き不向きを比較しながら、自分に合った選び方を解説します。
フランチャイズのメリットと制約
フランチャイズ(FC)に加盟して塾を開業する最大のメリットは、知名度のあるブランドでスタートできることです。既に信頼性のある名前とノウハウが揃っており、教材・カリキュラム・広告などのサポートも手厚いため、未経験者でも安心して始めやすいのが特徴です。
一方で、ロイヤリティの支払いや、指導スタイル・価格設定などに自由がないといった制約もあります。また、初期費用は個人開業よりも高めで、加盟金・研修費などを含めると100万〜300万円以上が一般的です。独自の運営が難しいことを理解した上で、「安心感」と「自由度」のバランスを考える必要があります。
個人経営で自由にやるか、支援を受けるか
完全に個人で塾を経営する場合、自分の教育理念を反映した授業や指導方針を自由に展開できるのが最大の魅力です。「大手の型にはまらない教育をしたい」「生徒に寄り添った指導がしたい」といった想いがある人には、個人経営が向いています。
一方で、「経営や集客に不安がある」「1人でゼロからやるのは心細い」という人には、一定の支援を受けられるFC型が安心材料になります。どちらが正解というわけではなく、自身の性格・目的・スキルに合った開業方法を選ぶことが重要です。後から法人化やFC化することも可能なので、まずは身の丈に合った方法でスタートするのが賢明です。
両者の収益モデル・費用比較
個人経営とフランチャイズ塾では、初期費用・ランニングコスト・収益性に明確な違いがあります。以下の表に代表的な比較をまとめました。
| 項目 | 個人経営 | フランチャイズ |
| 初期費用 | 約50万~200万円 | 約100万~300万円以上 |
| ロイヤリティ | なし | 月売上の5〜15%前後 |
| 教材・システム費 | 自由(工夫次第で節約) | 定額または指定教材の購入義務 |
| 広告・集客 | 自力で実施 | 本部サポートあり |
| 収益性 | 利幅大、リスクも大 | 利幅小、安定性あり |
| 回収期間の目安 | 半年〜1年 | 1年〜2年 |
個人経営は収益の全てを自分で得られる一方、集客や運営のすべてを自力で行う必要があります。フランチャイズは収益の一部をロイヤリティとして支払いますが、その分支援体制があり、初心者でも軌道に乗せやすいです。「独立性を重視するか」「安定を重視するか」で判断しましょう。
【体験談】実際に個人塾を立ち上げた人の声

実際に個人で塾を開業した方の体験談は、開業を目指す読者にとって大きな励みになることでしょう。ここでは、開業までの経緯や工夫、苦労と成功体験を通じて得たリアルな学びをご紹介します。
教員を辞めて開業したAさんの事例

もともと中学校の教員として10年以上勤務していましたが、「もっと一人ひとりの生徒に寄り添いたい」「型にはまらない指導がしたい」と感じ、思い切って退職しました。
退職後は数ヶ月かけて物件を探し、元教え子の保護者などの協力も得ながら地域密着の個別指導塾をスタート!
開業当初は「生徒が来なかったらどうしよう」という不安もめちゃくちゃありましたが、ありがたいことに前職で築いてきた信頼や口コミが広がり、半年後には定員の8割が埋まる状況まで何とかもっていけました。
今では「学校とは違う、自分の信じる教育ができている」と信じており、経営者としてのやりがいも感じています。
ゼロから月商80万円に到達したBさんの事例

教育業界未経験で、資金もノウハウもない状態から塾を開業しました。最初は自宅の一室を使って月謝8千円の少人数制英語塾をスタートさせ、ターゲットを「英検3級を目指す中学生」に絞ったことで、ニッチなニーズにマッチし、近隣の保護者から徐々に認知されていきました!
特に意識したのは「口コミ」と「SNS活用」。体験授業後にはLINEで丁寧に感想を聞き、満足度の高い保護者には自分からガツガツ口コミ投稿をお願いしてましたね(笑)
Instagramでは授業風景や生徒の合格実績を写真付きで発信したところ、紹介が紹介を呼んで生徒数が急増していき、1年半後には月商80万円を突破するまでに成長させることができました。
1年で閉塾してしまったCさんの事例

個人で学習塾を開業したものの、1年で閉塾を余儀なくされました。原因の1つは、物件選びの失敗だったと思います。
駅から遠く、アクセスが悪い場所に教室を構えたことで、生徒や保護者にとって通いにくい印象を与えてしまい、結果的に体験後の入塾率が極端に低かったです。
また、後から分かったことですが、チラシや広告の訴求ポイントが曖昧で、「何が強みの塾なのか」が伝わっていなかったことも要因でした。私自身、「もっと市場調査をしてターゲットを明確にすべきだった」と反省しています。
現在はその経験をもとに、他塾にてマーケティング支援を行なっています。失敗から学べることは非常に多く、準備の段階での戦略設計の重要性を再認識させられました。
まとめ
個人で塾を経営することは、自由度が高い反面、責任やリスクも伴う挑戦です。しかし、しっかりと準備し、自分の強みや地域ニーズに合った運営ができれば、やりがいある仕事として大きな成果も得られます。まずは一歩踏み出して、できることから行動してみましょう。教育への想いが原動力になります。

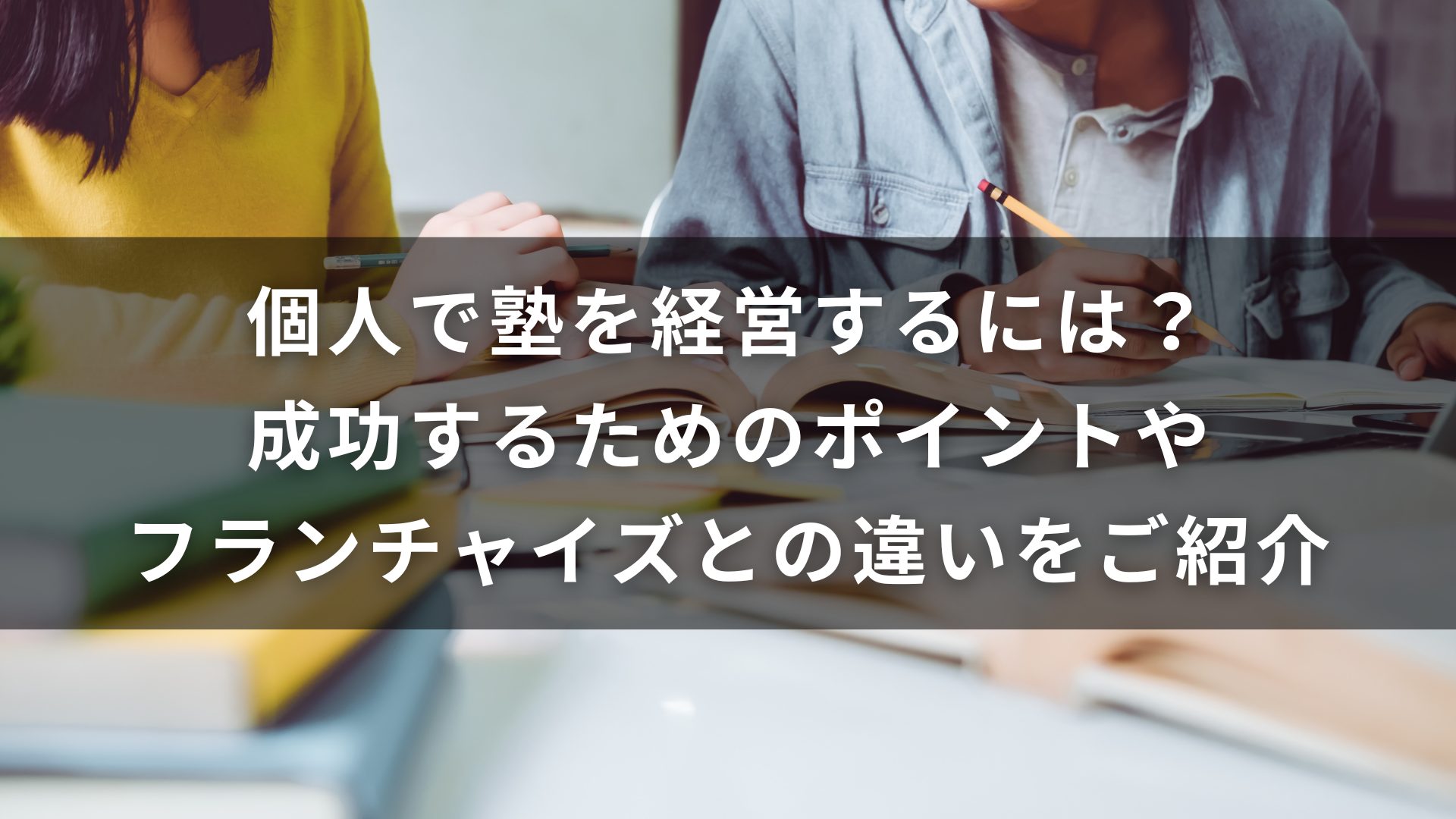
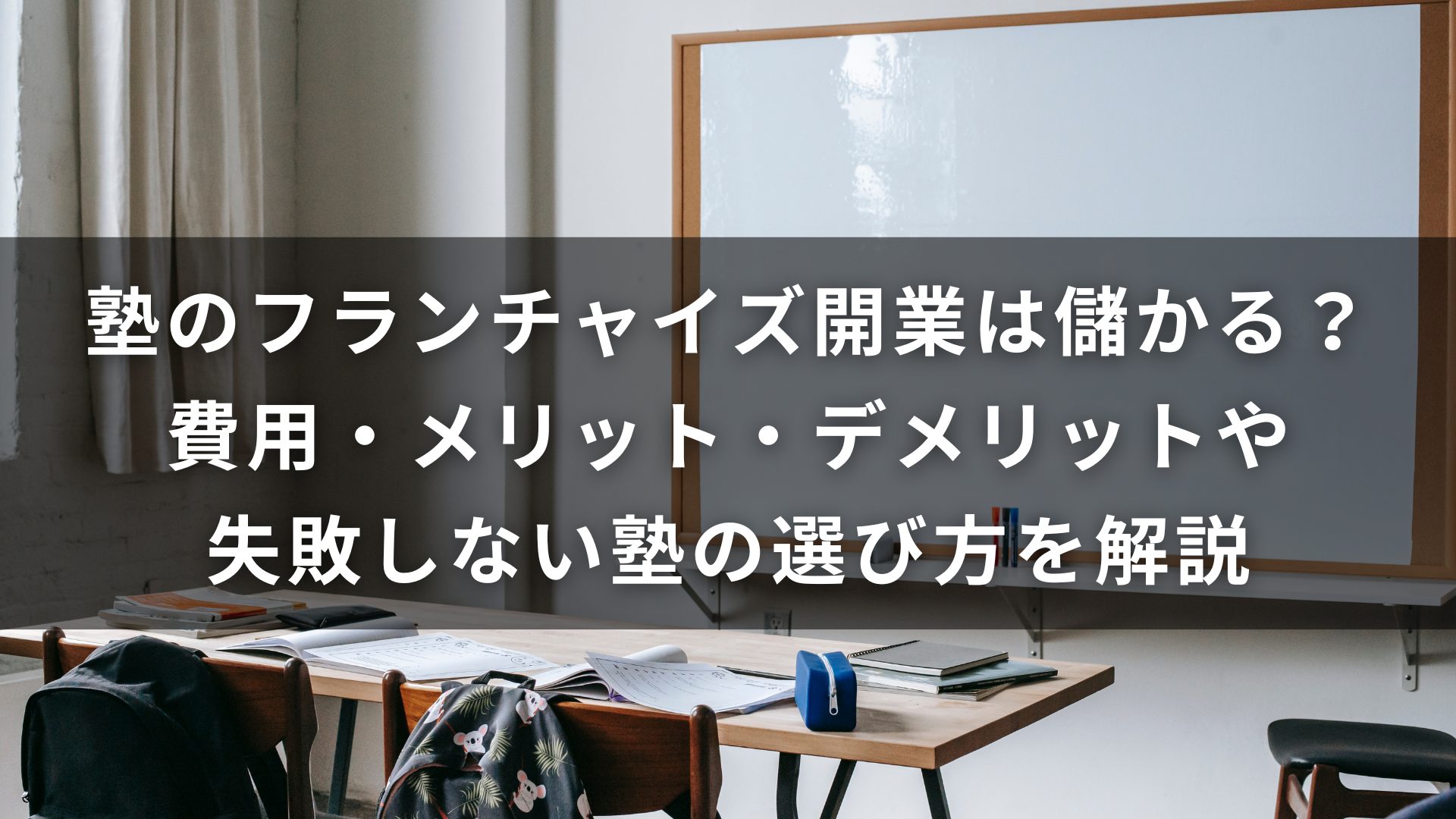
コメント