大学生の間でよく耳にする「長期インターン」ですが、具体的にどういうもので、どのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか。今回は、実際に長期インターンを経験した学生の声や実態調査をもとに、長期インターンの定義や学生が感じるリアルなメリット・デメリットをわかりやすく解説します。
これから長期インターンへの参加を検討している方に向けて、自分に合ったインターンを見極めるためのヒントをお届けしますので、ぜひチェックしてみてください。
長期インターンとは?メリットを知る前に押さえたい基礎知識

ここでは、長期インターンに参加する前に知っておきたい基本情報を解説します。短期インターンとの違いや、参加対象、働き方の特徴を押さえることで、メリットの理解がより深まります。
長期インターンの定義と期間
「インターンシップ(インターン)」とは、学生が企業で実際に働く経験を積む制度のことを指します。インターンは大きく分けて「長期インターン」と「短期インターン」の2種類です。
長期インターンは、一般的に1ヶ月以上の継続的な勤務を伴うもので、参加期間は企業や制度によって異なります。多くのケースでは、明確な期間を設けず、大学卒業まで継続して勤務するスタイルが取られることもあります。この点はアルバイトと共通する部分です。
また、短期インターンと異なり、長期インターンではシフト制が導入されており、時給が支払われるケースが多く、交通費の支給がある場合もあります。勤務頻度は企業によって異なりますが、週に数回、1日数時間からフルタイムまで、柔軟な勤務形態が一般的です。
短期インターンとの違い
短期インターンは、1日から2週間程度の期間で行われるプログラムで、スキル習得よりも企業や業務に対する理解を深めることが主な目的です。長期インターンとは異なり、シフト制ではなく全日程参加型である点が特徴です。さらに、給与や交通費が支給されないケースも多く見られます。
また、短期インターンは採用直結型(選考直結型)の一環として実施されることも珍しくなく、インターン中のパフォーマンスがその後の選考に影響を与える場合があります。一方で、長期インターンは選考とは無関係に参加できるケースも多く、その経験で培ったスキルを志望する別企業の選考で活かすといった活用の仕方も可能です。
参加対象と学年別の傾向
長期インターンに参加する学生は、主に大学2年生から3年生が中心です。就職活動を意識し始めるタイミングで参加するケースが多く見られます。
参加の目的は人それぞれですが、たとえば「アルバイトとは異なる裁量のある仕事を経験したい」「実務経験を通じてスキルを習得し、就活でアピール材料にしたい」といった声が多くあります。「生活費や趣味のために稼ぎたい」といった理由は比較的少なく、スキル習得や成長実感を求めて参加する学生が多い傾向にあります。
働き方・勤務スタイルの柔軟性
長期インターンの特徴の一つは、働き方や勤務スタイルの柔軟性にあります。前述の通り、長期インターンはシフト制が基本であり、学業やサークル活動と両立しやすいことがメリットです。
企業によっては最低限の勤務頻度が設定されている場合もありますが、シフトの自由度が高い企業も多く存在します。また、リモート勤務を導入している企業もあり、柔軟な働き方が可能です。たとえば、実家に帰省中で長期間出社できない場合でも、在宅で業務を継続できるケースがあります。
長期インターンのメリット【学生が得られる4つの成長】
ここでは、学生が長期インターンに参加することで得られる主なメリットを4つの視点から解説します。キャリア形成、スキル習得、社会人との関わりなど、将来に直結する成長の機会が得られます。
実務経験を積んでスキルが身につく
企業や制度によって内容は異なりますが、長期インターンで得られる実務経験には営業やマーケティングなどがあります。
・営業職では、コミュニケーション能力や粘り強さを養うことができます。
・マーケティング職では、傾聴力・分析力・課題解決力などが求められ、これらを実践の中で身につけることができます。
いずれにしても、任される業務ごとに習得できるスキルは異なりますが、現場に直結する実践的な力を培えるのが長期インターンの大きな強みです。大学卒業後に企業へ就職する際には、こうしたスキルが即戦力として評価される可能性が高くなります。
社会人との接点・基本スキルが得られる
長期インターンでは、業務に関するスキルのみならず、社会人との関わりが生まれることで、ビジネスマナーなど社会人において基本的なスキルが得られます。
任される業務によっては、学生だけで完全に遂行することは難しく、社員の方と協力しながら遂行することが少なくありません。その場合、社会人との接点が生まれることになるので、ビジネスの場における言葉遣いや態度などの「ビジネスマナー」を学生のうちから学ぶことになります。ビジネスマナーは実際に社会人として働く時だけでなく、就活などでも必要になるので、早いうちから学んでおいて損はありません。
就活でアピールできる材料が増える
就職活動において、エントリーシート(ES)や面接で頻出する質問のひとつに「学生時代に力を入れたこと(いわゆるガクチカ)」があります。この質問では、取り組みを通じて何を学び、どのように成長したか、そしてそれを社会人としてどう活かしていくかを具体的かつ論理的に説明することが求められます。
その点、長期インターンは実務経験に基づく取り組みであるため、得られるスキルが企業での業務に直結しやすく、説得力のあるエピソードとしてアピールしやすいのが特徴です。ビジネスマナーや社会人としての基本的な行動様式も身につけられるため、選考時においても即戦力としての期待を持たれやすい傾向があります。
また、長期インターンの経験を通じて、自分の適性や働き方への理解が深まり、業界・職種選びの軸が明確になる学生も多く見られます。結果として、志望動機や自己PRの内容にも具体性が増し、就職活動全体において有利に働くケースが多いと言えるでしょう。
キャリア意識が深まり、将来の方向性が見えてくる
長期インターンは1年、あるいは数年にわたる継続的な取り組みとなることも多く、自身の向き不向きや適性について深く理解できる貴重な機会となります。任される業務も幅広いため、活動を通じて自分の性格やスキル、興味関心が明確になってくるケースが少なくありません。こうした気づきは、将来の進路選択に大きく影響を与える要素となります。
たとえば、長期インターンのなかでマーケティングに適性を見出した学生が、広告代理店やマーケティング系のコンサルティングファームを志望するようになるといったケースもあります。このように、実務経験に基づいてキャリアの方向性が定まることで、就職活動全体における選択の精度も高まっていくでしょう。
企業が感じる長期インターンのメリットとは?

ここでは、企業側が長期インターンを導入することで得られるメリットを、「育成」と「採用」の視点から解説します。
学生の視点やアイデアが得られる
企業にとってのメリットの1つは、若年層である学生ならではの新鮮な発想や消費者視点を取り入れられることです。業務に携わるメンバーの多様化が進むことで、従来にはなかった新たなアイデアが生まれたり、学生の視点を活かした取り組みが可能になります。たとえば、ある事業のターゲット層が学生や若年層である場合、当事者ならではの視点が大きな強みとなり、的確なアプローチが生まれることで企業成果にもつながる可能性があります。
戦力としての育成・即戦力化ができる
長期インターンを採用活動の一環として活用する企業も増えています。インターン期間中に実務を通じて学生を育成することで、入社後すぐに活躍できる即戦力候補として期待できる点が特徴です。研修コストや教育工数を削減できるだけでなく、一般的な選考フローから入社する人材と比べて、より高いスキルと業務理解を備えた人材を確保できる可能性があります。
入社前のマッチングが可能になる
長期インターンを通じて、企業側は学生の適性やポテンシャルを長期的に見極めることができます。これは、短期インターンや面接などの短期間の選考よりも、人物像を深く理解できる手段として有効です。
一方、学生側も企業の業務内容・社風・職場の雰囲気などをリアルに体験でき、自身との相性を判断しやすくなります。その結果、企業と学生の相互理解が進み、入社後のミスマッチを防ぐことができます。
近年では、早期退職や退職代行の利用が増加しており、企業にとってもリスク回避が重要課題となっています。そのため、長期インターンによる事前のマッチングは、人材定着の観点からも注目されています。
体験談でわかる!長期インターンのリアルな学びと後悔
ここでは、実際に長期インターンに参加した学生の体験をもとに、感じたメリットや就活への影響、後悔した点などを紹介します。
やってよかったと感じた瞬間
長期インターンに参加して良かった点として、特に印象的だったのが以下の2点です。
①異なる立場の人とのコミュニケーション機会が増えたこと
②社会人としての自分を深く理解できたこと
まず①について、長期インターンでは異なる大学・学部に通う学生や企業の社員との関わりが多くあります。これにより、年齢や立場の異なる相手との自然な接点が増え、対人スキルが養われたという実感があります。
②の「自分の理解」については、インターンで実際の業務に取り組むことで、仕事における自分の適性や苦手分野を具体的に把握できました。これはアルバイトやサークル活動では得づらい経験であり、今後のキャリア選択に役立つ重要な学びとなりました。
インターン経験が就活に役立ったケース
長期インターンは企業での就業経験があることから、エントリーシート(ES)や面接で話の具体性が増し、採用担当者に伝わりやすい内容になりやすい点が大きな利点です。
特に、実務を通して得たスキルや行動体験は、他の学生との差別化につながりやすく、質問が深堀りされるきっかけにもなります。実際、面接官からの質問の多くがインターン経験に関するものだったというケースもあります。
ESや面接の通過率も、同年代の就活生と比較して明らかに高かったことから、長期インターンの経験が選考においてプラスに働いたと考えられます。
後悔したこと・失敗から得られた学び
長期インターンにおける失敗は数えられませんが、ここでは2つ挙げます。
1つ目は、「執筆業務において、主観的な意見を盛り込みすぎて文章が抽象的・難解になってしまった」ケースです。たとえば、自社メディアなどのコラム執筆を任された学生が、自分の意見を優先するあまり読者目線を欠いた内容になってしまい、上司や担当者から書き方を繰り返し指摘されるといったことがあります。こうした経験を通じて、「伝わる文章」の書き方や、第三者に配慮した情報発信の姿勢を身につける学生も少なくありません。
2つ目は、「ビジネスコミュニケーションに不慣れで、適切な相槌やリアクションが取れなかった」ことです。インターン開始当初は、会話中に無言で聞き続けることが丁寧だと思い込んでいた学生が、実際のミーティングの場面で「反応がないと意思疎通が難しい」と指摘を受け、徐々に相槌や頷きなどのリアクションを意識するようになった事例もあります。こうしたビジネスマナーは、実際の現場で失敗を通じて学ぶことが多い領域です。
長期インターンのデメリット・注意点も知っておこう
ここでは、長期インターンに潜むリスクや注意点について解説します。参加前に知っておくことで、後悔や失敗を防ぐことができます。
学業や私生活との両立が難しい場合がある
長期インターンは、アルバイトのようにシフト制で勤務するケースが多いものの、企業によっては最低出勤日数や時間が厳しく設定されていることがあります。たとえば、ある学生のケースでは「週15時間以上、かつ平日のみ勤務が必須」といった条件が課されていた企業も存在しました。
こうした長時間の勤務が必要なインターンでは、大学の授業や課題提出との両立が難しくなり、単位を落とすリスクも生じかねません。
そのため、長期インターンを検討する際は、本業である学業に無理なく取り組める環境かどうかを十分に確認することが大切です。また、企業によっては学生の事情に配慮し、柔軟にシフトを調整してくれる場合もあるため、不安がある場合は事前に相談してみるとよいでしょう。
雑用ばかりで成長につながらないケースもある
一部の企業では、本来期待されるような実務経験ではなく、雑用やルーティン作業が中心になるケースがあります。たとえば、ある学生は長期インターンでテレアポ業務のみを繰り返し担当させられ、実務的なスキルが得られないまま辞めてしまったという経験をしていました。
このような環境では、スキルアップにつながらず、貴重な時間を浪費することになりかねません。
こうした事態を防ぐためには、長期インターン先の企業を選ぶ段階で、説明会や企業HP、口コミサイトなどを活用して、実際の業務内容をしっかりとリサーチすることが重要です。また、インターン中に業務に関する希望がある場合は、社員に対して他の業務にも挑戦したい旨を丁寧に伝え、適性や興味に合った業務を経験できるよう相談してみるのもひとつの方法です。
ブラック企業に巻き込まれるリスク
一部の企業において、営業インターンなどで過度な成果を求められたり、学生にとって過重なノルマが課されるケースがあります。こうした状況はプレッシャーとなり、精神的なストレスや「燃え尽き症候群」のような状態につながることもあり、精神衛生上のリスクを伴います。加えて、極端に待遇が悪いインターン先も存在するため、十分な注意が必要です。
このようなリスクを回避するためには、企業の口コミ情報を確認したり、求人内容を細かく読み込んだりするなど、事前の丁寧な情報収集が欠かせません。
目的が曖昧なままだと時間を無駄にする
「とりあえず参加しておけば就活で有利になりそう」といった曖昧な目的のまま長期インターンに参加すると、実務経験を通じて得られるスキルや知識を十分に吸収できない可能性があります。その結果、時間だけを浪費し、長期インターン本来の価値を活かせないことになりかねません。
参加前には「なぜこのインターンに参加したいのか」を改めて見直し、自分なりの明確な目的を設定することが大切です。
後悔しないためのインターン先の選び方とリスク回避術
ここでは、長期インターン先を選ぶ際に確認すべきポイントと、信頼できる企業を見極める方法について解説します。
無理のないスケジュールを組む
無理のないスケジュールを組むには、勤務日数や勤務時間などについて、求人票や面接時に必ず確認することが大切です。可能であれば、実際に参加した友人や先輩からの情報も参考にしながら、自分の他の活動と両立できるかを慎重に検討しましょう。
業務内容・サポート体制を事前に確認する
企業とのミスマッチを防ぐためにも、インターン開始前に業務内容やサポート体制を明確にしておきましょう。
業務内容では、「具体的にどんな業務を任されるのか」「ノルマはあるのか」「求められるスキルは何か」などを確認することが重要です。サポート体制については、「学生と社員の関わり方」「業務に対するフィードバックの有無」などをチェックしましょう。
目的やゴールを明確にしておく
自分の目的やゴールが明確であれば、業務内容とのギャップが起こりにくく、モチベーションの維持にもつながります。長期インターンを実りあるものにするためにも、目指す姿から逆算して目的を具体化しておくことが大切です。
例えば、コミュニケーション能力を高めたい場合は「社員との連携を通じてコミュニケーション力を鍛えたい」というように設定できます。将来的に広告代理店を目指している場合は、「マーケティングスキルを磨くために、広告業務に携わるインターンに参加する」といった形で目的を明確にしましょう。
口コミ・評判を活用して企業を見極める
長期インターンに関する情報を集める際には、専門の口コミサイト(例:Voilなど)を活用するのがおすすめです。「Voil」は長期インターンの口コミを扱う業界初のサービスとして知られています。
また、OB・OG訪問をしたい場合は、大学のキャリアセンターを活用したり、ビズリーチ・キャンパスやMatcherなどのOB訪問サービスを利用するのも有効です。
まとめ
この記事では、長期インターンのメリットやデメリットについて紹介しました。
長期インターンのメリットは、参加する人により大きく左右されます。ただ、長期インターンのメリットを最大化できる人は、「行動する人」です。自分の目標やゴールに向けて何が必要なのか考えて、どう行動することが重要なのか常に意識しながら動ける人こそが長期インターンを心から「やってよかった」と感じることができるはずです。
この記事の内容が、長期インターンを後悔しないものに変える要因になれば幸いです。

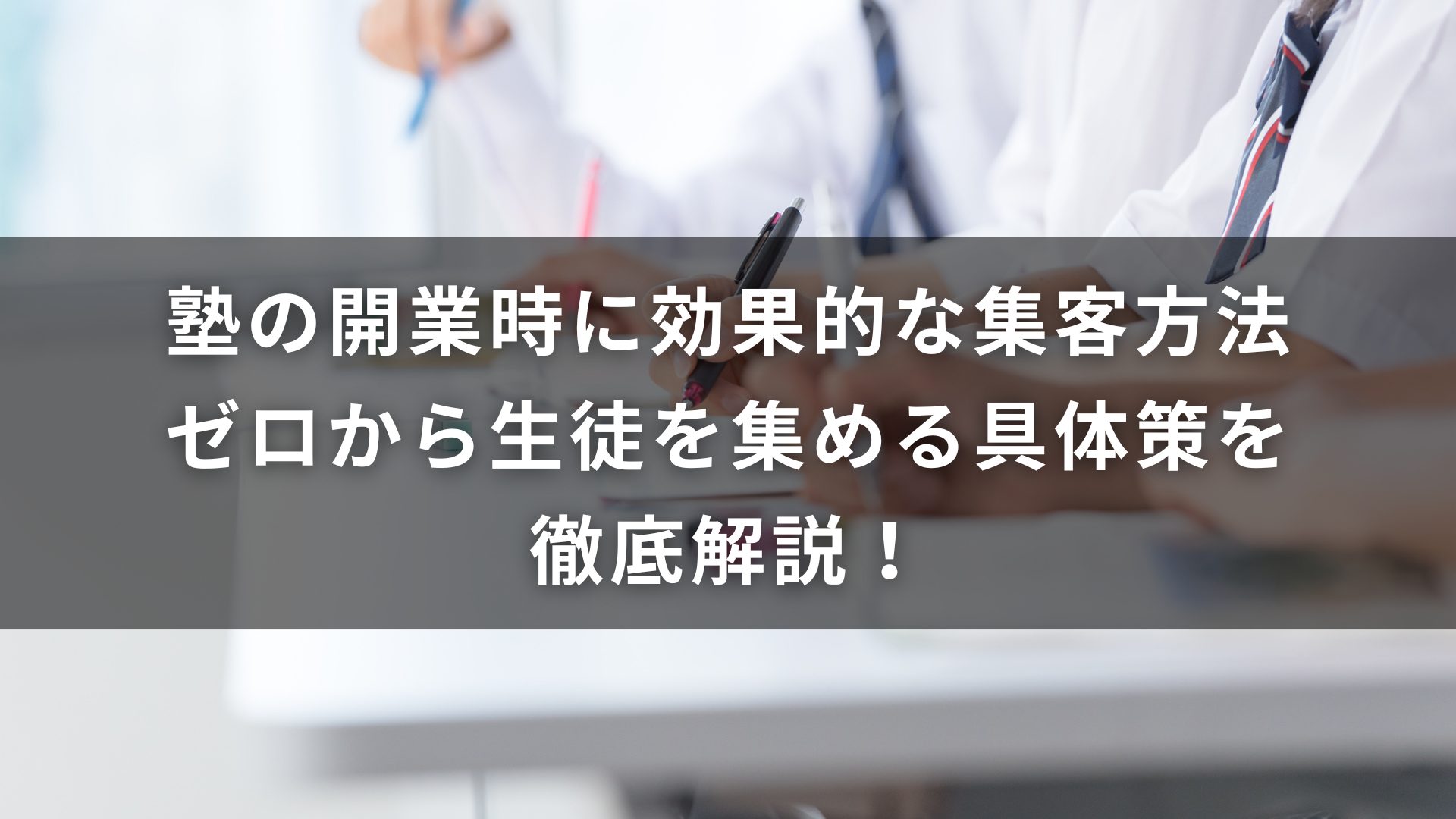


コメント