インターンシップの選考で最初の関門となるエントリーシート(ES)は、「何を書けばいいのかわからない」「志望動機や自己PRがまとまらない」と悩む学生も多いでしょう。本記事では、インターン用ESの基本構成や頻出設問の書き方、企業が重視するポイント、通過率を高めるための具体的な例文まで、網羅的に解説します。よくある失敗パターンやその改善策、Q&A形式での疑問解消など、実践的なノウハウも盛り込みましたので、ぜひご確認ください。
インターンのエントリーシートとは?

インターンシップのエントリーシート(ES)は、学生の意欲や適性を判断する重要な書類です。以下の内容を正しく理解し、適切に準備しましょう。
選考ステップにおける役割とは?
インターン選考において、エントリーシートは最初の関門です。企業はESを通じて、学生の志望度や適性、コミュニケーション能力を判断します。また、ESの内容は面接での質問のベースにもなるため、自己PRや志望動機を明確に伝えることが重要です。ESは単なる書類ではなく、自己表現の場であることを意識しましょう。
本選考との違い(気軽さ・内容の深さなど)
インターンのESと本選考のESでは、求められる内容や深さに大きな違いがあります。インターンでは、学生の興味・意欲・基本的なコミュニケーション能力を重視する傾向がある一方で、本選考では、より具体的なスキル・経験・企業とのマッチ度が問われます。そのため、インターンのESは過度に構えず、自分の言葉で素直に表現しましょう。
提出時のフォーマットやルールは?
エントリーシートの提出形式は、企業によって異なります。一般的には、Webフォームへの入力やPDFファイルのアップロードが主流ですが、中には手書きを求める企業もありますので、募集要項をよく確認しましょう。また、文字数制限やフォーマットの指定がある場合も多いため、提出前には、誤字脱字や形式のチェックが必須です。
よくある設問と書き方のポイント
インターンのエントリーシートでは、志望動機や自己PR、ガクチカなどがよく問われるため、それぞれの設問の意図を理解した効果的なアピール方法を解説します。
志望動機の書き方とNG例
志望動機では、「なぜこの企業のインターンに応募したのか」を明確に伝えることが重要です。企業研究を行い、自分の興味や将来のキャリアと企業の特徴を結びつけましょう。抽象的な表現や他社でも通用するような内容はNGです。具体的なエピソードや企業の取り組みに触れることで、説得力のある志望動機になります。
自己PRの書き方と構成テンプレート
自己PRでは、自分の強みや特性を具体的なエピソードとともに伝えたいため、「結論(強み)→具体例→学びや活かし方」が基本的な構成になります。例えば、「協調性がある」という強みをアピールする場合、チームでの経験やその中での役割を具体的に述べましょう。企業が求める人物像を意識し、自分の強みがどのように活かせるかを示すことが重要です。
学生時代に頑張ったこと(ガクチカ)の書き方
ガクチカは、企業があなたの価値観や行動特性を知るための重要な項目です。単なる成果だけでなく、取り組む過程で直面した課題や、それをどう乗り越えたかを具体的に描写しましょう。得られた学びや成長を明確に示すことで、企業に対する貢献意欲もアピールできるはずです。具体性と自己分析を重視した構成が、説得力のあるガクチカを作る鍵となります。
【例文付き】インターン用エントリーシートの回答9選
インターンシップのESでは、具体的なエピソードを通じて強みや志望動機を伝えることが求められます。以下ではタイプ別の例文を紹介しますので、参考にしてみてください。
志望動機の例文3選(志望軸別)
ここでは、志望動機が分かりやすく書かれている例文を、志望軸別に3つ紹介していきます。
業界理解を深めたいタイプの場合
私が貴社のインターンシップに応募した理由は、「IT業界の現場を体感し、業界理解を深めたい」と考えたからです。大学では情報工学を専攻しており、特にAI技術に興味があります。講義や研究を通じて、AIが医療・教育・行政など多様な分野に応用されていることを知り、より実践的な視点から学びたいという思いが強まりました。
貴社はAIを活用したソリューション開発に力を入れており、社会課題に対して真摯に取り組んでいる点に惹かれました。AIを「人の生活をより良くする手段」として捉えている姿勢にも共感しています。
私は、学内プロジェクトでチャットボット開発に携わった経験があります。ニーズに合わない回答が多発したため、アンケート調査を通じて改善点を洗い出し、シナリオを修正するなど試行錯誤を重ねました。この経験から、技術力だけでなくユーザー視点の重要性も実感しました。
インターンでは、実務を通してIT業界の仕事の流れやチームでの協働を学びたいと考えています。現場で得た知見を今後の学びやキャリア選択に活かしたいです。
企業理念に共感するタイプの場合
私が貴社のインターンシップに応募したのは、企業理念に強く共感したからです。貴社の「テクノロジーで人々の生活を豊かにする」というミッションは、私が大学生活で大切にしてきた価値観と一致しています。
大学では、地域商店街のPR活動に携わるプロジェクトに参加しました。現地でヒアリングを重ねながら課題を把握し、SNS活用による情報発信の改善提案を行いました。この経験から、単にスキルを発揮するのではなく「誰かの役に立つ視点」で働きかけることに大きなやりがいを感じるようになりました。
貴社は地域社会との連携を重視しながら、多様な事業に取り組んでおり、私の価値観や経験と親和性が高いと感じています。特に、若手でも新規事業に関われる柔軟な組織文化にも魅力を感じました。
インターンを通じて、貴社の考え方や仕事の進め方を深く理解し、今後の就職活動の軸を固めるヒントを得たいと考えています。積極的に現場で吸収し、成長につなげていきたいです。
職種への関心が強いタイプの場合
私は将来、マーケティング分野で活躍することを目指しており、その第一歩として貴社のインターンシップに応募しました。大学では消費者行動論を中心に学んでおり、特にデジタルマーケティングに興味を持っています。
ゼミでは、地元企業と連携し、Instagramを活用したキャンペーンを立案・実行しました。ターゲットの選定から投稿内容の設計、効果測定までを一貫して行い、キャンペーン期間中に来店者数が増加する成果を得られました。この経験を通じて、「仮説を立てて検証する思考」や「成果につながる工夫」を実践的に学びました。
貴社は、データを活かしたマーケティング戦略に強みを持ち、BtoCのみならず教育や医療など幅広い分野で実績がある点に魅力を感じています。インターンでは、自分の知識がどの程度通用するのかを確かめたいと同時に、現場で必要なスキルを体感的に学びたいです。
短い期間ではありますが、積極的に行動し、自分の課題を見つける姿勢で取り組んでいきたいと考えています。
自己PRの例文3選(性格タイプ別)
次に、自己PRが分かりやすく書かれている例文を、性格タイプ別に3つ紹介していきます。
「チームのまとめ役」タイプ
私の強みは、周囲との協調を大切にしながら、チーム全体が前向きに動けるように働きかけられる点です。大学のゼミ活動で、異なる価値観のメンバーとともに地域課題をテーマにした研究プロジェクトに取り組みました。
プロジェクトでは、方向性の違いからメンバー間で意見が対立する場面が多くありましたが、進行が滞ってしまった時期には、「一人ひとりの考えを整理して共有できれば、全体がまとまる」と考え、自らファシリテーター役を買って出ました。話し合いの前にアンケート形式で全員の意見を集約した上で、「共通している部分」「優先すべき視点」などをまとめ、可視化し続けた結果、チーム内の意思疎通が円滑になり、最終的には全員が納得するプレゼンを完成できました。発表では高い評価を得ると同時に、「あなたがいたからチームがまとまった」と言ってもらえたことが、大きな自信につながりました。
インターンでも目立つ役割に限らず、周囲と連携して前向きな雰囲気づくりに貢献しながら、実践的なコミュニケーション力をさらに高めていきたいです。
「主体的なチャレンジャー」タイプ
私の強みは、まず行動してみる「実行力」と、臆せずチャレンジできる姿勢です。2年生の頃、学内のボランティア団体に興味を持ち、発足メンバーとして活動を開始しました。
活動内容や運営体制が未整備の中、私は「自分にできることを探し、動いてみる」ことを意識し、まずは地域清掃イベントの提案書を作成しました。また、イベントの流れや必要な備品、協力団体の候補などを調べてまとめ、リーダーに提案しました。さらに、企画を通すには地域住民や大学側との調整も必要でしたが、「最初の一歩を誰かが踏み出さないと始まらない」と考え、関係者との連絡・交渉も同時進行で積極的に担当しました。
結果として、初回イベントを無事に実施することができ、今までにない達成感とともに「動けば、周囲も動く」という感覚を得られました。
インターンにおいても、指示を待つだけでなく、目の前の課題に自ら関わり、主体的に行動できる存在でありたいです。自分の行動がチームや業務に良い影響を与えられるよう、積極性と柔軟性を持って取り組みます。
「堅実な努力家」タイプ
私の強みは、コツコツと努力を続ける「継続力」です。TOEIC500点台だった入学時に「英語力を伸ばしたい」と思い、800点を目標に学習を始めました。当初は文法問題に苦戦しましたが、「毎朝30分だけ勉強する」と決め、小さな習慣からスタートしました。
単語学習にはアプリを使い、通学時間も有効活用。途中でモチベーションが下がらないよう、SNSで学習進捗を記録したり、同じ目標を持つ友人と定期的に模試を受けたりと、飽きずに継続できる仕組みを工夫しました。試験のたびに弱点を分析し、学習法を改善しながら進めた結果、約1年後には835点を取得でき、大きな自信につながりました。
この経験から、私は成果がすぐに出なくても「地道に継続すること」の大切さと、それを支える工夫の必要性を理解しています。インターンでは、最初から即戦力として働けるわけではないと思っていますが、与えられた業務や課題に対して丁寧に取り組み、粘り強く成果を出せるよう努めます。短期間でも成長を実感できるよう、継続的な努力を決して惜しみません。
学生時代に頑張ったことの例文3選(活動ジャンル別)
最後に、学生時代に頑張ったことが分かりやすく書かれている例文を、活動ジャンル別に3つ紹介していきます。
飲食店でのアルバイト
私は飲食店でのホールスタッフのアルバイトを通じて、「現場の課題を自ら見つけ、改善する力」を身につけました。当時勤務していた店舗はランチタイムの混雑が激しく、オーダーミスや提供の遅れが頻発していました。私自身も、忙しさに追われてお客様に迷惑をかけることがあり、「どうすればこの状況を改善できるのか」を考えるようになりました。
そこで私はミスの原因が「誰が何を担当しているか曖昧であること」だと判断し、シフト表と連動してその日のキッチン・ホール・ドリンク担当を視覚化&共有できるシフト管理アプリの導入を提案することで、業務中のミスや混乱を大幅に減少させることに成功しました。
また、この取り組みをきっかけに系列店が同様の施策を導入し、オーナーから特別な賞をいただくこともできました。この経験から、課題に気づき、現場目線で解決策を考え、周囲を巻き込んで実行に移すことの大切さを学びました。インターンでも、小さな違和感を見逃さず、前向きな提案ができる存在でありたいと考えています。
サークルの副リーダー
私は大学のダンスサークルで副リーダーを務め、100名超のメンバーをまとめて発表会を成功に導いた経験があります。発表会は年1回、約半年かけて準備する大規模イベントで、私の代は例年より人数が多く、練習の参加率や連絡の行き違いが課題でした。
このままでは完成度に影響が出ると感じた私は、「全体練習以外の時間でも練習できる仕組み」を整えました。個々の予定に合わせた少人数制の補習練習を設け、欠席者でも動画や振付メモを共有できるようにしました。さらに、情報共有の質を上げるため、連絡手段のLINEに加えてGoogleカレンダーやドライブを併用するよう提案しました。
その結果、練習の参加率は大きく改善し、発表会も無事成功。審査員から「最も一体感があるチームだった」と評価をいただき、メンバー全員の努力が実ったことを実感しました。この経験を通じて、周囲の状況を見て必要な仕組みを整える力、組織全体を前向きに動かすサポート力を身につけました。インターンでも、チームの目標達成に向けて柔軟に動ける存在を目指したいです。
ゼミ活動
私は大学3年次のゼミ活動で「地域商店街の集客改善」をテーマにフィールドワークを担当し、提案力と実行力を磨きました。チームでの研究では、地元商店街の集客力低下に関して仮説を立て、ヒアリングやアンケートを通じて課題を掘り下げました。
特に私が注力したのは、アンケート設計と集計・分析です。調査を効果的に行うため「どんな情報を得たいか」「どう聞けば答えてもらえるか」を明確にし、質問の順番や選択肢の表現に細心の注意を払いました。最終的に、10代~30代の若年層の利用率が極端に低いことが判明し、「情報発信の不足」や「SNSでの認知の弱さ」が浮かび上がりました。
私たちは「商店街公式Instagramの開設」や「店舗情報のショート動画化」などを提案。実現可能性とターゲットの明確さが評価され、一部が商店街連合会に採用されました。この経験から、課題の本質を捉える力と、定量・定性の両面から考える力を養いました。インターンでも、現場の声を丁寧に拾い、実効性のある提案ができるよう尽力します。
内容は悪くないのに落ちる人の共通点と、その解決策

「しっかり書けているはずなのに通過しない…。」そんなESには、共通する“もったいないポイント”があります。ここではその原因と解決策をわかりやすく解説します。
どこかで見たような表現になっている
エントリーシートが埋もれてしまう最大の要因は、「よくある表現」に頼ってしまうことです。「貴社の理念に共感しました」「学びたいと思いました」など、抽象的で誰でも言えそうな言葉では印象に残らないため、「どの部分に」「なぜ共感したのか」など、自分の経験や視点を具体的に絡めましょう。ありきたりな表現を自分の言葉に変える意識が重要です。
経験だけに頼って“伝わっていない”
次にありがちなのが、経験の事実だけを並べてしまうパターンです。「部長を務めました」「大会で入賞しました」といった実績は一見魅力的ですが、それだけではあなたの人柄や成長が伝わりません。「その経験で何を学んだか」「どんな姿勢で取り組んだのか」に言及し、単なる結果ではなくプロセスと思考を深掘りして評価されやすい内容を心がけましょう。
「企業視点」が抜けてしまっている
自己PRや志望動機が「自分語り」で終わっている場合も、選考では通過しにくくなります。大切なのは、「この学生が企業にとってどんな価値があるか」という視点です。応募企業の業種や特徴を理解し、「自分の経験がどう貢献できるか」を示すことで、良いESに仕上がります。企業HPや採用ページを読み込み、相手に合わせた内容設計を意識しましょう。
【Q&A】エントリーシートに関するよくある悩み
エントリーシートに関する悩みや疑問は尽きないものです。ここでは、学生からよく寄せられる質問とその解決策を、Q&A形式で紹介します。
文字数制限に足りない場合/多すぎる場合の対処法は?
設問の文字数に対して「足りない」と焦る学生や、「書きたいことが収まらない」と悩む学生は多いでしょう。足りない場合は、根拠となるエピソードや学びを補足してボリュームを持たせ、多すぎる場合は、構成を見直して伝えたい要素に絞るのが効果的です。「起承転結」を意識しつつ、重要な部分がきちんと伝わるよう調整してみてください。
自己PR・志望動機が1つにまとまっている時の書き方のコツは?
例えば「あなたの自己PRと志望動機を200字以内で答えてください」といった設問では、情報の取捨選択がカギになります。まずは簡潔に自分の強みを述べた後、それが応募企業でどう活かせるかという形で志望理由に接続すると、自然な流れが生まれるでしょう。すべてを詰め込もうとせず、伝えたい軸を明確にして書くことが重要です。
「ESで落ちた原因」はどこで振り返るべき?
ESの時点でインターン選考に落ちた際、「なぜ通らなかったのか分からない」といった悩みの原因を探るには、読み手視点でのチェックが効果的です。例えば、「内容が抽象的ではなかったか」「構成はわかりやすかったか」「企業の特性と結びついていたか」などを振り返ることで改善点が見えてきます。信頼できる第三者に読んでもらうのも1つの手でしょう。
まとめ
インターンシップのエントリーシートは、就活本番の練習という位置づけではありますが、丁寧に取り組むことで「伝える力」や「自分の軸」の整理にもつながります。大切なのは、形式よりも「あなたらしさ」がにじむことです。自分の経験をどう捉え、相手にどう伝えるかを意識すれば、たとえ派手な実績がなくても十分に魅力的な文章になるでしょう。本記事の例文や構成を参考に、自分の言葉で納得のいくESを仕上げてみてください。

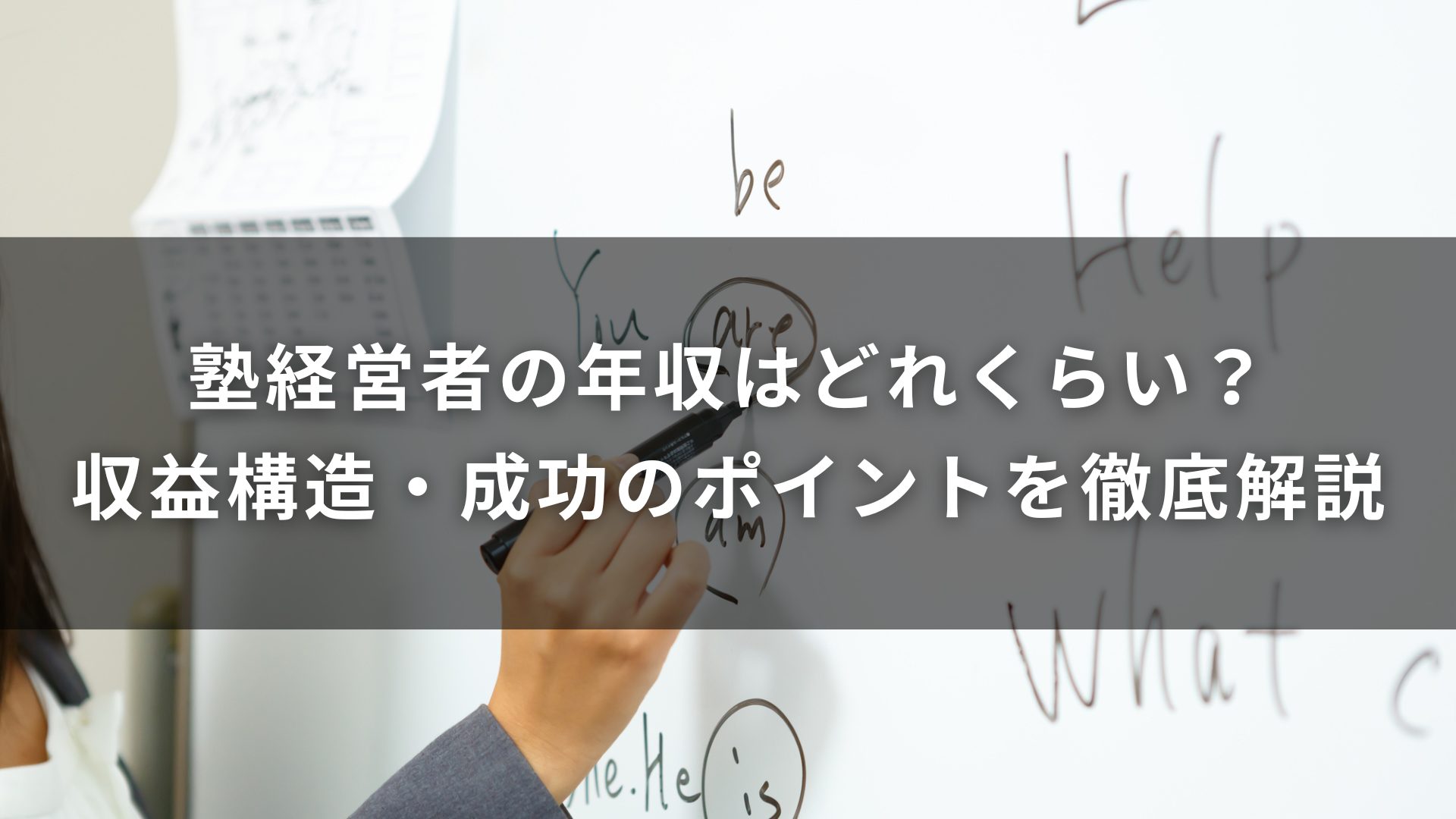
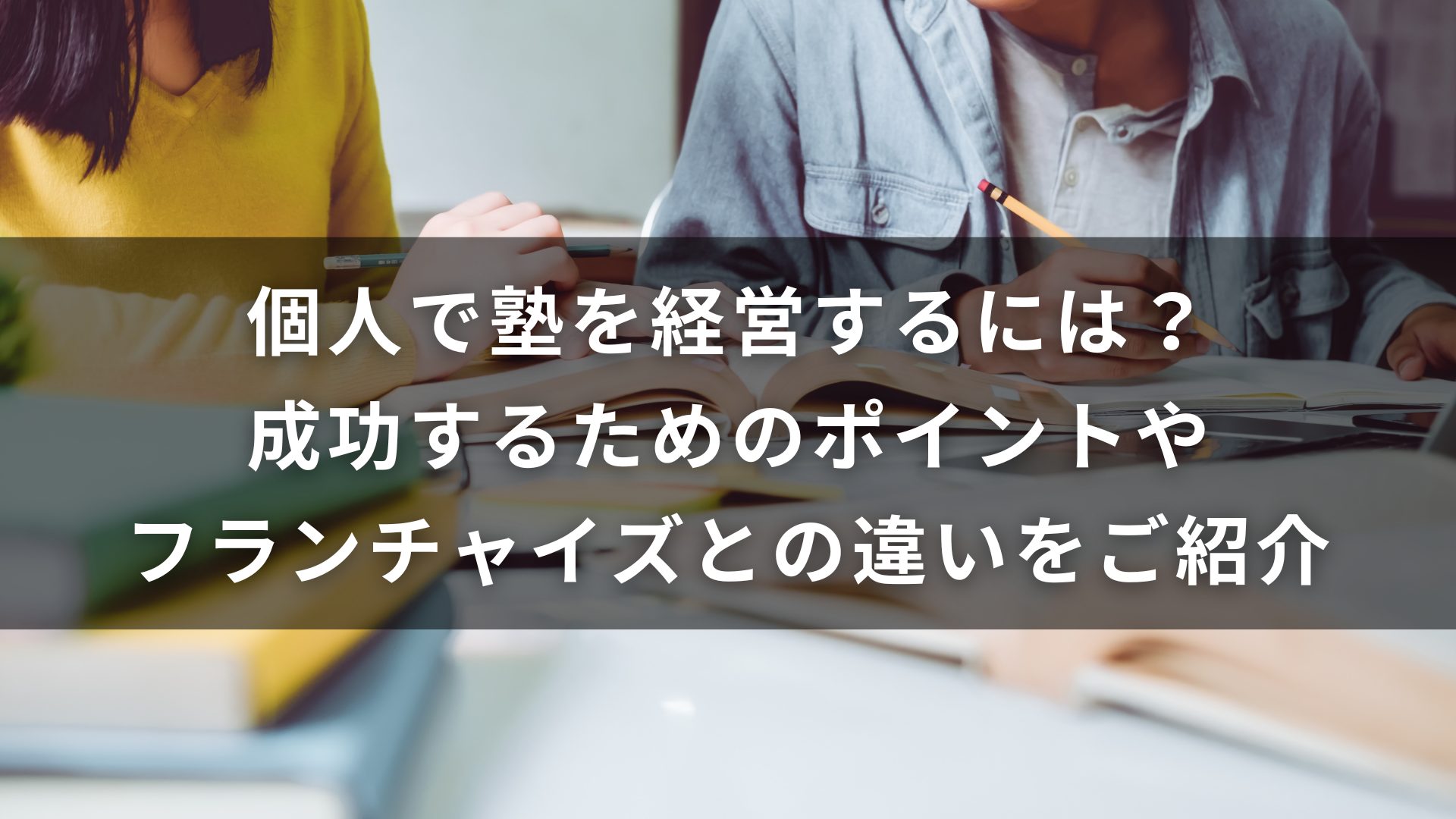

コメント