「少子化で生徒が集まらない…」「周りの塾が次々と閉鎖している…」「このままでは、うちの塾も終わりかもしれない…」
学習塾を経営する中で、このような不安に駆られていませんか?メディアでは「学習塾の倒産が過去最多」といったニュースが報じられ、塾経営の将来に暗い影を落としています。
しかし、本当に塾経営は「終わり」なのでしょうか。
結論から言えば、やり方次第で未来は大きく変わります。確かに市場環境は厳しく、旧態依然とした経営では立ち行かなくなる塾が増えているのは事実です。一方で、時代の変化を捉え、戦略的に経営を行うことで、むしろ成長を続けている塾も数多く存在します。
この記事では、塾経営の厳しい現状をデータで直視し、なぜ多くの塾が潰れるのか、その原因を徹底分析します。その上で、厳しい環境を乗り越え、あなたの塾が「選ばれる塾」として生き残るための具体的な経営戦略を、成功事例とともに詳しく解説します。
この記事を読めば、漠然とした不安が解消され、明日から何をすべきかが見えてくるはずです。
学習塾の倒産・廃業の実態

まずは、学習塾業界が直面している厳しい現実を、客観的なデータで見ていきましょう。
最新の倒産件数とその推移
近年、学習塾の倒産は増加傾向にあります。株式会社帝国データバンクの調査によると、2023年度の学習塾の倒産件数は45件にのぼり、これまで最多だった2020年度の35件を上回り、過去最多を更新しました。
特に、小規模な事業者が多い「学習塾」業界は、コロナ禍でのオンライン化の遅れや、物価高によるコスト増が経営を圧迫し、倒産件数を押し上げる一因となっています。この数字は、多くの塾経営者が危機感を抱いている現状を裏付けるものと言えるでしょう。
(参考:帝国データバンク「学習塾」の倒産、2年連続で増加 2023年度は過去最多の45件)
倒産理由の内訳と主な要因
倒産の主な理由として最も多いのが「販売不振(売上不振)」です。これは、生徒数が減少し、売上が立たなくなったことが直接的な引き金になっているケースが大半を占めます。
具体的には、以下のような要因が複雑に絡み合っています。
これらの要因が重なり、じわじわと経営を圧迫し、最終的に事業継続が困難になる塾が後を絶たないのです。
大手塾と個人塾での傾向の違い
倒産や廃業の傾向は、塾の規模によっても異なります。
【大手塾】
全国展開する大手塾では、経営不振に陥った特定の校舎を閉鎖する「不採算事業の整理」という形が多く見られます。会社全体が倒産するケースは稀ですが、競争の激しいエリアからの撤退は頻繁に行われています。
【個人塾】
個人塾や中小規模の塾では、売上不振に加えて「後継者不足」による廃業も深刻な問題です。塾長が高齢化し、事業を引き継ぐ相手が見つからずにやむなく塾を閉めるケースが増えています。また、大手のような資本力や組織力がないため、一度経営が傾くと立て直しが難しいという側面もあります。
塾経営が厳しくなる・潰れる原因

なぜ、これほど多くの塾が経営難に陥り、潰れてしまうのでしょうか。その背景には、業界全体を取り巻く構造的な問題が存在します。
少子化による生徒獲得の困難化
塾経営が厳しくなる最大の原因は、やはり「少子化」です。文部科学省の学校基本調査によると、小中学生の数は長期的に減少傾向にあります。
これは、学習塾にとってメインターゲットとなる顧客のパイそのものが縮小していることを意味します。昔と同じやり方で生徒募集をしていても、対象となる子どもの数が減っているため、生徒が集まりにくくなるのは必然と言えるでしょう。限られた生徒を多くの塾が奪い合う、熾烈な競争時代に突入しているのです。
大手・個別指導塾との競争激化
学習塾市場は、プレイヤーの多様化により競争が激化しています。
このような状況下で、特徴のない個人塾や中小塾は、価格競争やサービス競争に巻き込まれ、消耗戦を強いられがちです。
オンライン化への対応の遅れ
コロナ禍をきっかけに、教育現場のオンライン化は一気に加速しました。映像授業やオンラインでの個別指導は、もはや特別なものではなく、当たり前の選択肢となっています。
しかし、デジタル化への投資やノウハウの蓄積が遅れた塾は、この変化に対応できませんでした。オンライン指導を求める生徒や保護者のニーズを取りこぼし、商圏を対面に限定してしまった結果、生徒獲得の機会を大きく損失しているのです。
多様化する教育ニーズへの不適合
かつて塾の役割は「学校の補習」や「受験対策」が中心でした。しかし、現代の保護者や生徒が塾に求めるものは、それだけではありません。
このように多様化・高度化する教育ニーズを捉えきれず、旧来型の知識詰め込み型の指導しか提供できない塾は、次第に時代遅れと見なされ、選ばれなくなってしまいます。
経営が傾く塾に共通する特徴

厳しい外部環境に加え、経営が傾く塾には内部的な問題、つまり「経営上の特徴」が共通して見られます。自塾に当てはまる点がないか、チェックしてみてください。
【明確な強みや差別化戦略の欠如】
「うちの塾の強みは何ですか?」と聞かれて、即答できない塾は危険信号です。「地域密着」「アットホーム」といった曖昧な言葉だけでは、数ある塾の中から選ばれる理由にはなりません。「〇〇中学校のテスト対策なら絶対に負けない」「医学部受験の化学に特化している」といった、具体的で明確な強みが必要です。
【効果的な集客・広報活動の不足】
今でもチラシのポスティングや口コミだけに頼っていませんか?もちろんそれらも重要ですが、現代の保護者はスマートフォンで情報を集めるのが当たり前です。WebサイトやSNS、塾検索サイトなどを活用したデジタルマーケティングに取り組まなければ、そもそも塾の存在を知ってもらうことすらできません。
【どんぶり勘定の財務管理】
毎月の売上や支出を正確に把握していますか?損益計算書(PL)や貸借対照表(BS)を見て、経営状況を分析できていますか?感覚だけに頼った「どんぶり勘定」では、気づいたときには手遅れになっている可能性があります。特にキャッシュフロー(現金の流れ)の管理は重要で、帳簿上は黒字でも現金が不足して倒産する「黒字倒産」のリスクも潜んでいます。
【旧態依然とした指導方法と教材】
塾長の長年の経験則だけに頼った指導や、何年も更新されていない古い教材を使い続けている塾は、生徒の成績を伸ばす力が弱まっている可能性があります。最新の入試トレンドや教育メソッドを常に研究し、指導の質をアップデートし続ける姿勢がなければ、生徒や保護者の信頼を失ってしまいます。
学習塾の市場規模と将来性

厳しい話が続きましたが、学習塾業界の未来は決して暗いだけではありません。市場全体の動向と、今後の可能性について見ていきましょう。
学習塾市場規模の最新データと推移
株式会社矢野経済研究所の調査によると、2022年度の学習塾・予備校の市場規模は、事業者売上高ベースで前年度比1.2%増の9,520億円と推計されています。
少子化にもかかわらず市場規模が横ばい、あるいは微増で推移しているのは、子ども一人あたりにかける教育費が増加しているためです。公教育への不安や、より良い教育を受けさせたいという保護者の思いが、塾への支出を支えています。つまり、市場から需要が消えたわけではなく、むしろ質の高い教育へのニーズは高まっているのです。
(参考:矢野経済研究所「学習塾・予備校市場に関する調査(2023年)」)
受験産業の現状と今後の課題
大学入学共通テストの導入や学習指導要領の改訂など、入試制度や学校教育は常に変化しています。これに伴い、塾に求められる指導内容も変化します。
今後の課題は、こうした変化にスピーディーに対応し、新しい評価軸(思考力・判断力・表現力など)に対応した指導を提供できるかどうかです。従来の知識暗記型の受験対策だけでは、いずれ通用しなくなるでしょう。
これからの学習塾に求められる役割
これからの学習塾は、単に勉強を教える場所ではなく、生徒一人ひとりの未来をデザインするパートナーとしての役割が求められます。
このような付加価値を提供できる塾こそが、これからの時代に必要とされ、生き残っていくことができるでしょう。
厳しい環境で生き残る塾経営戦略

では、具体的にどのような手を打てば、厳しい競争を勝ち抜き、塾を成長させることができるのでしょうか。明日から実践できる5つの経営戦略をご紹介します。
ターゲットを絞る専門特化戦略
「誰にでも」対応しようとすると、結果的に「誰からも」選ばれなくなります。自塾の強みを活かせる特定の分野にターゲットを絞り込み、その領域で圧倒的なNo.1を目指す「専門特化戦略」が有効です。
専門特化することで、指導の質が向上し、口コミも広がりやすくなります。結果として、高くても通いたいと思ってもらえるブランド力を築くことができます。
オンライン指導の導入と活用法
オンライン指導は、もはや大手だけの専売特許ではありません。小規模な塾でも、Zoomなどのツールを使えば簡単に導入できます。
プログラミング等、新ニーズへの対応
既存の教科指導に加えて、新しい教育ニーズに応える講座を開設することも有効な戦略です。特に、2020年度から小学校で必修化されたプログラミング教育は、市場の伸びが期待できる分野です。
これらの講座をフックに新しい生徒層を獲得し、既存の教科指導へとつなげていくことも可能です。
保護者満足度を高める連携強化策
塾経営の安定には、生徒の成績向上はもちろんのこと、保護者からの信頼を獲得することが不可欠です。保護者満足度を高めることで、退塾率の低下や、口コミ・紹介による新規入塾につながります。
「ここまで手厚く見てくれるのか」という感動が、塾の強力なファンを生み出します。
M&Aによる事業承継という選択肢
もし後継者が見つからず、事業の継続に不安を感じているのであれば、M&A(合併・買収)によって第三者に事業を譲渡するという選択肢も検討する価値があります。
廃業すれば全てがゼロになってしまいますが、M&Aであれば、これまで築き上げてきた塾のブランドやノウハウ、そして何より大切な生徒たちを、次の経営者に引き継ぐことができます。これは、経営者自身にとっても、従業員や生徒にとっても、前向きな「ハッピーリタイア」となり得ます。近年は、塾業界専門のM&A仲介サービスも増えています。
経営難を乗り越えた塾の成功事例

最後に、厳しい状況からV字回復を遂げた塾の事例を3つご紹介します。自塾の戦略を考える上でのヒントにしてください。
地域密着で差別化した個人塾
生徒数が減少していたある個人塾は、「〇〇中学校の定期テスト対策専門塾」へと大胆に方針転換。過去問を徹底的に分析し、学校の先生の出題傾向まで把握した「超・地域密着」の指導を展開しました。その結果、「〇〇中のテスト対策なら、あの塾しかない」という評判が広まり、大手塾に通っていた生徒が転塾してくるまでになりました。
オンライン特化で全国展開した塾
地方都市で小規模な塾を経営していた塾長。コロナ禍を機に、全ての指導をオンラインに切り替えました。対面では集客が難しかったニッチな「古文・漢文専門」の指導をオンラインで提供したところ、全国から受講希望者が殺到。今では、場所にとらわれずに質の高い教育を届ける人気塾へと成長しました。
特定科目に特化しブランド化した塾
理系科目が苦手な生徒が多かったある塾は、「苦手な子専門の数学塾」としてリニューアル。「わかるまで、とことん付き合う」をモットーにした丁寧な指導が口コミで評判に。数学の成績が上がった生徒が、他の教科も受講するようになり、結果的に塾全体の売上アップにつながりました。
まとめ
「塾経営は終わり」という言葉は、変化を恐れ、旧来のやり方に固執する塾にとっては現実のものとなるかもしれません。少子化や競争激化という厳しい現実は、決して避けては通れない課題です。
しかし、この記事で見てきたように、学習塾の市場そのものがなくなったわけではありません。むしろ、子ども一人にかける教育費は増加し、質の高い教育へのニーズは高まっています。
重要なのは、この厳しい現実を直視し、変化の波を捉えることです。
これらの戦略を実行することで、あなたの塾は単に生き残るだけでなく、地域で「なくてはならない存在」として輝き続けることができます。
塾経営は「終わり」ではありません。むしろ、新しい価値を創造できる塾にとっては、大きなチャンスが広がる「始まり」の時代です。まずは自塾の現状を冷静に分析し、未来に向けた一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

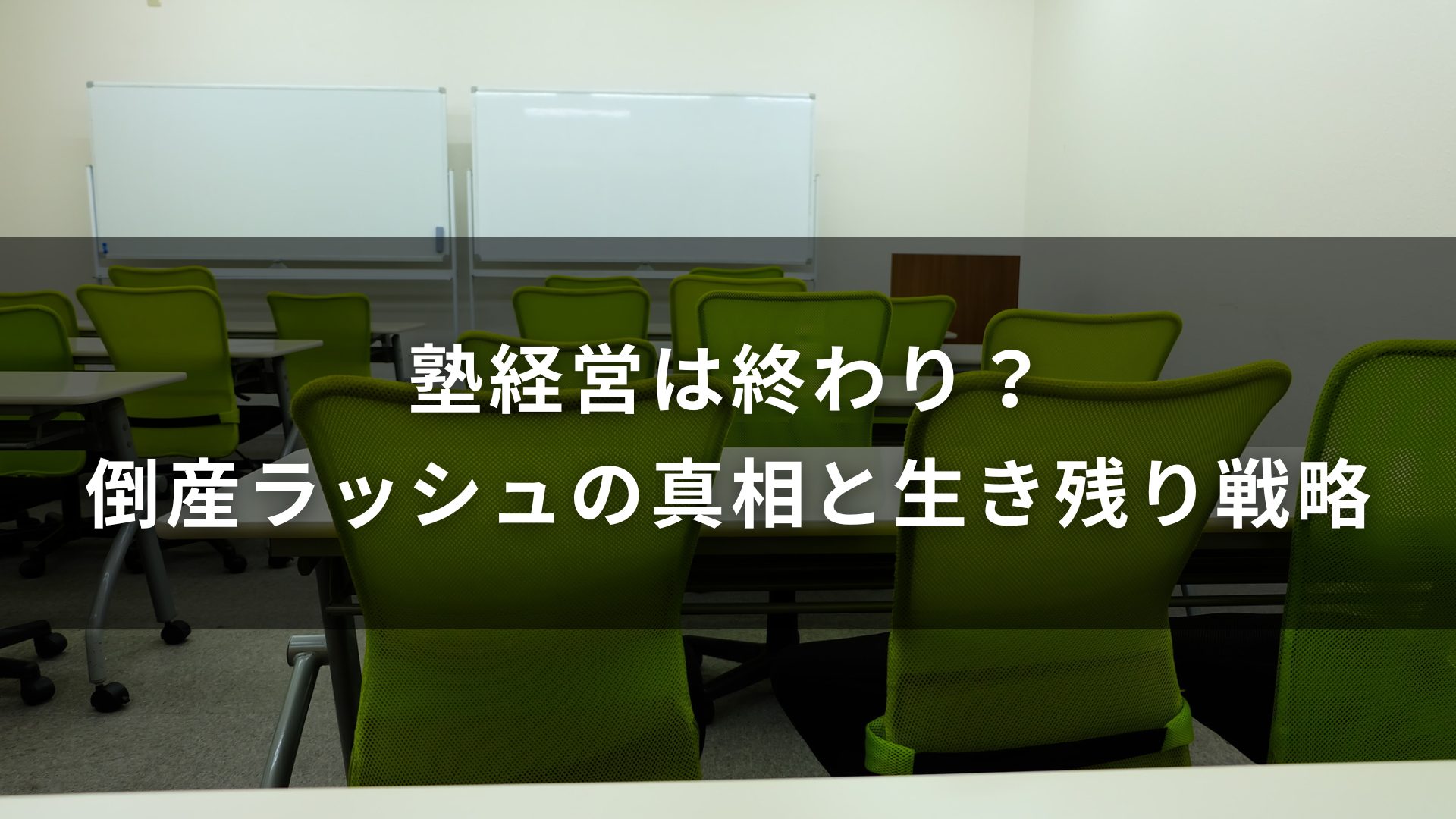
-20.jpg)
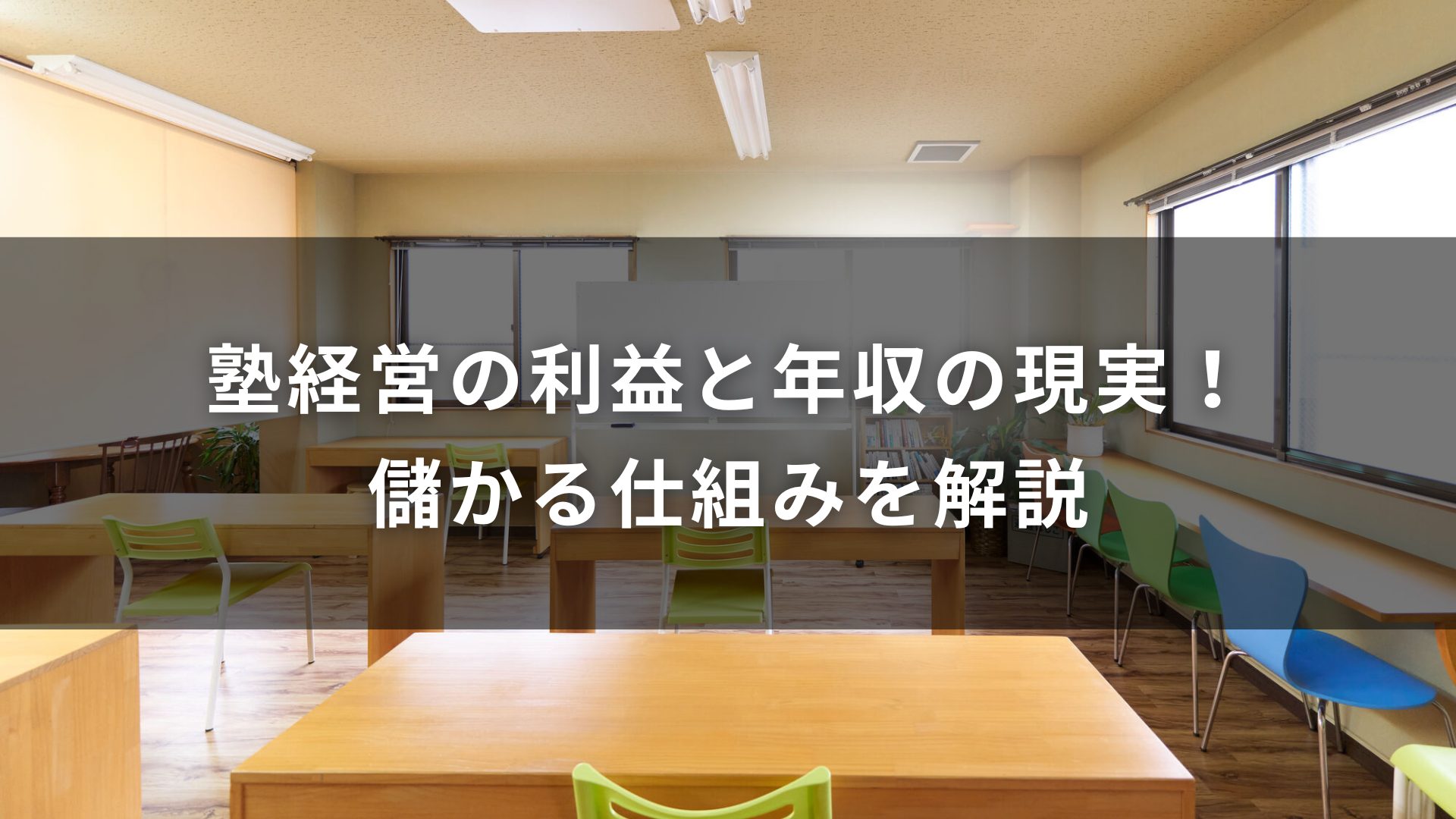
コメント