高校生でもインターンシップに参加できる時代。将来の進路選択や社会経験に役立つと注目されつつも、「どこで探せばいいの?」「本当に参加できるの?」と不安を感じている人も多いのではないでしょうか。本記事では、高校生のインターンシップについて、基本的な仕組みや探し方、参加のメリット・注意点、実際の体験例までをわかりやすく解説。さらに、保護者や学校との関わり方や将来への活かし方についても丁寧に紹介します。高校生活のうちにインターンを経験する意味を、一緒に考えてみましょう。
高校生のインターンシップとは?まずは基本を理解しよう

ここでは、「インターンシップとは何か」やその特徴について解説します。インターンシップについて初めて聞いた方もいれば、大学生のインターンシップをイメージしていた人も多いと思いますが、実は高校生の方でも参加できるプログラムは多くあります。
そもそもインターンシップとは何か?
インターンシップとは、企業や団体で実際の仕事を体験する制度のことを言います。参加者が将来のキャリア(人生)を考える上で、企業や業界について理解を深めたり、職業に対する適性を調べたりするための、実践的な学びの場として提供されています。基本的には大学生のイメージが強いですが、高校生や転職を検討している社会人向けのインターンシップもあります。それぞれ制度や内容などが異なっています。
高校生でも参加できるの?大学生との違いは?
大学生向けのインターンシップは就職活動を控えた大学3年生や大学院生が夏休みや冬休みの長期休暇を利用して参加するものが多いです。1日〜2週間程度の短いものから、1ヶ月以上、1年以上にわたる長期のものまであります。内容は企業に対する理解や、学生のコミュニケーションスキル等の人物評価に主眼を置いたものが多いです。グループワークでの企画提案、社員による講義、実際の現場での仕事体験、自社サービスの開発業務など、多岐に渡ります。また、企業の採用選考に直結する場合もあります。
一方で高校生向けのインターンシップは、学校の授業外や部活動外の時間に参加する必要があるため、大学生に比べて期間が限られる傾向にあります。通常は3日〜5日程度と言われています。内容は大学生と異なり、職場見学、簡単な補助作業、グループワーク、セミナー形式での業界説明などが中心となります。働くことのイメージを掴むことや、社会人としてのマナーやコミュニケーション能力を学ぶことに主眼が置かれています。また、報酬がないものであることがほとんどなので、アルバイトが禁止されている高校の生徒でも参加することができます。
どんな業界や企業が受け入れているのか
高校生が参加可能なインターンを開催している業界は、主にIT業界や公務員、NPO法人等が挙げられます。IT業界だと、ベンチャー企業を中心に様々な企業でプログラムを設けています。公務員も多くの自治体で設けられています。例えば千葉県庁、福岡県庁、厚木市役所等が挙げられます。NPO法人も多数開催されています。中には政治家の体験をできるインターンなどユニークなものまであります。
高校生がインターンに参加するメリットと注意点
ここでは、高校生がインターンシップに参加する意義や利点、参加時に気をつけたい点を紹介します。インターンシップには多くのメリットがありますが、参加にあたっては慎重に検討する必要があります。
進路選びに役立つリアルな経験ができる
インターンでは、リアルな社会経験を積むことができます。インターン先の企業や業界について深く理解することができるため、将来の進路選択において重要な判断材料となります。例えば自分の気になっている業界の企業のインターンに参加した場合、実は自分の思っていたものと違うものだと気づいたり、反対に自分の考え方にぴったりの業界であることに気づいたりします。また、自分の気になっている業界の企業でなくとも、実は自分の適性に合っていたり、当初思っていたよりも魅力的な業界だと思ったりして、思わぬ発見がある場合があります。このようにインターンで得られた気づきや経験は、将来の進路選択で重要な役割を果たすでしょう。
自己PRや志望動機にも活かせる
インターンの経験を通して、自分の得意なことや苦手なこと、興味のあることがわかるようになります。これは大学受験の総合型選抜や、就職活動において自己PRを求められた際、話す材料になります。
特に就職活動においては、自己PRだけでなく志望動機も重視されます。その場合、自らのインターン経験に紐づけられた具体的な内容のものを話せるようになります。
学業や部活との両立は可能?リスクや注意点も解説
インターンへの参加を検討する際は、学業や部活と両立できるかどうかを意識してください。インターンは数日単位で行われるものが多いので、休日や長期休暇に参加することをおすすめします。特にスポーツ系の部活に所属している方は、体力的負担を考慮してインターンに参加してください。おすすめの時期は、大会までまだ時間のある時期や、冬などのオフシーズンです。
高校生インターンの探し方と申込みの流れ

ここでは、インターンについて「どう探すの?」や「申し込みは難しい?」という疑問に答えるため、高校生インターンの探しかたと申し込みの流れについて解説します。
学校経由・自治体・民間サービスなどの探し方
インターンを探す際は、学校経由、自治体、民間サービス経由で探すことがおすすめです。
学校経由で探す場合
一部の学校では、進路指導室や先生が企業と連携し、インターンシップ先を紹介することがあります。
信頼性が高く、学業との両立がしやすいプログラムが多いことが特徴です。過去に実績のある地元企業や、学校のカリキュラムに合わせた就業体験に参加できます。
自治体経由で探す場合
都道府県や市町村が、地域の企業やNPO法人と連携してインターンシッププログラムを提供することがあります。また、その自治体の職員(公務員)としてのインターンシップを経験することもできます。
地域に根ざした多様な業種・職種に触れる機会がある点が特徴です。市役所での公務員体験や、地域のNPOでの社会貢献活動ができます。
民間サービス経由で探す場合
専門のインターンシップ募集サイトや、企業の採用・CSRページ、求人サイトなどで探せます。
幅広い選択肢から、自分の興味や関心にあったインターンシップを探せることが特徴です。IT企業のエンジニア体験、Webサイト作成、SNSマーケティングの補助など、できる活動は多岐に渡ります。
申込み方法・必要書類・保護者の同意は必要?
高校生がインターンに申し込む際の流れや必要書類等は学校経由、自治体、民間サービス経由で申し込む場合で異なります。
学校経由で申し込む場合
多くの場合、進路指導室や学年主任の先生から、校内掲示板、生徒向け説明会、または担任の先生を通じてインターンシップの募集案内があります。
興味のあるインターンシップが見つかったら、まずは担任の先生や進路指導の先生に相談し、参加の意思を伝えます。
次に学校所定の「インターンシップ申込書」「参加同意書(保護者署名入り)」などの書類を提出します。学校によっては履歴書や志望理由書の提出を別途求められる場合があります。
最後に学校が企業や団体に生徒を推薦します。場合によっては書類選考や面接が実施されることもあります。参加が決定したら、学校から生徒本人と保護者へ連絡があります。
自治体経由で申し込む場合
各自治体の教育委員会や産業振興部署のウェブサイト、広報誌、または地域の高校を通じて募集情報が公開されます。
興味のあるプログラムが見つかったら、オンラインフォーム、郵送、またはFAXで申込を行います。多くの場合、「氏名・学校・学年・連絡先・志望動機」などが必要事項となっています。また、保護者の同意が必要となる場合がほとんどです。申込多数の場合は、書類選考や面接、小論文などで選考する場合があります。
民間サービス経由で申し込む場合
インターンシップ募集サイトや企業の採用・CSRページから求人情報を探します。
興味のあるプログラムが見つかったら、応募資格や実施期間、内容、場所、報酬の有無などを確認しましょう。報酬がある場合、学校がアルバイトを禁止していると参加できない可能性があるので注意してください。また、プログラムによって保護者の同意や学校の許可が必要な可能性があるので、必ず確認するようにしましょう。
応募にあたっては、多くの場合オンラインの応募フォームに必要事項を入力するか、履歴書や志望理由書をメール経由で提出します。志望理由書の書き方は、以下のページを参考にしてください。大学生向けのページですが、高校生の方でも参考になります。
スケジュール管理と心構え
インターン参加前は、体調管理をしっかりしてください。体調管理は企業との間で信頼関係を築くのに必要なことです。また、インターンと他の予定が被らないようにしっかりスケジュール調整を行いましょう。例えば部活の大事な大会や、予備校の模擬試験など重要な予定は特に被らないようにしてください。
インターン参加にあたっては、「積極的に学ぶ姿勢」「挨拶と感謝の気持ち」「責任感を持って取り組むこと」「失敗を恐れず挑戦すること」「目的意識」を忘れないようにしてください。
実際のインターン先ってどんなところ?事例でイメージしよう
この章では、インターン先について「どのような企業・団体にいくのかイメージできない」という方の疑問に答えるため、具体的な例をあげながら解説していきます。
人気のあるインターン先の業種や仕事内容
高校生に人気のインターン先としては、県庁などの官公庁、IT企業などが挙げられます。
千葉県庁のインターンシップでは、県立美術館や県立博物館、農業関係の部署や土木建築関係の部署など、受け入れ部署は多岐に渡ります。主に業務体験や職場見学を経験することができます。
IT企業では、プログラミングやコンピューターグラフィック、営業など体験できる業種は多岐に渡ります。プログラミングについて実際にプロの方から学んだり、実際の営業マンから営業の極意について学んだりすることができます。
高校生の体験談・口コミを紹介
ここでは、より高校生インターンについての理解度を上げるために、複数の事例や口コミを紹介したいと思います。
事例1:IT企業・高3女子
<業務内容>
3日間のインターンで、長期休暇を利用して参加。プログラミングの体験が主で、最後はプレゼン発表とフィードバックが行われた。
このインターンを通じて、①Javascript(アプリなどを動作させるために必要なコマンド=プログラミング言語の一種)の使い方、②アプリの詳しい開発方法、③コミュニケーションについて学んだ。
<感想>
「インターンシップへの参加するのは初めてだったのですが、こんなにプロフェッショナルな環境でやるとは思っておらず、経験した全てのことが想像以上でした。」
自分でネットで調べて取り組むことと、会社という環境に入って取り組むことは、環境もプロセスも全然違いました。そのような環境に触れることができて、嬉しかったです。」
https://sakurug.co.jp/news/19227/
事例2:風景デザイン業・高3男子
<業務内容>
2週間のインターン。通っていた高専の先生からの紹介で参加。パワーポイント資料の修正、音声の文字起こし(会議の議事録?)、イベント運営の協力を任された。また、その会社がデザインした広場や工事現場、デザインの打ち合わせの様子を見学できた。
<感想>
「とにかく感じたことが、実務の現場では学校でできない学びが溢れているということです。高専で勉強していてどんな建物や公園、広場も誰かがデザインしているんだと言うことは知っていましたが、インターンに行ったことでそれをどんな人たちがどんな風に働いて出来上がっているのかとリアリティーを目の当たりにすることができ、感動しました。学校では教えてもらえないような、そんなことまで考えて設計しているのかと言う驚きと学びで溢れていました。」
「事務所の方には忙しい中にも関わらず本当に親切にしていただきました。17歳の自分でもできる仕事を振ってくださったのはもちろん、17歳だからと舐めずに専門的な難しいプロジェクトの話まで丁寧に教えてくださいました。また毎日のようにお昼ご飯に連れて行ってもらってたくさん話を聞いてもらえました。一番びっくりだったのは最終日に事務所の代表の方と夕食をご一緒させて頂いたことです。事務所を立ち上げた背景やランドスケープとは何か、言ってはいけないような秘密の話まで僕を子供扱いせずに気さくに話してくださいました。」
「僕はこのインターンを通して何となく興味があっただけの分野にどっぷりとハマりました。『自分がやりたいことはこれだ!』と早い段階で決められたのもインターンに行ったことがきっかけです。」
https://note.com/dreamy_zebra3450/n/nb00d4d62e2c2
事例3:コンサルティング業・高3女子
<業務内容>
期間不明(長期インターン?)。主にマーケティングに携わっていて、顧客と直接コミュニケーションを取るなど、幅広い裁量を持ちながら従事。職業体験がメインで、他のインターンよりも任される業務の幅が広い。
<感想>
「ミスをして注意されることもありましたが、それをきっかけに仕事に対する向き合い方を学び、責任感、起こしたミスへの対処法を身につけることができました。(要約)」
「私がインターンシップを始めたのが高校3年生なのですが、よく『今から始めなくても良いんじゃないか』とか『高校生でインターンやるなんて早いね』と言われてきました。就活対策としてのインターンシップだったとしたら、そうなのかもしれませんが私は、就活対策のためではなく『自己成長』を目的としたインターンシップだったので年齢や学年関係なく受け入れてくれる長期インターンシップに『早すぎる』というのは無いと思っています。むしろ成長過程として、いずれ必ず経験しなければいけない事なのであれば早く経験することに越したことがないと思いますので、自分に自信を持ちたい人は是非参加してみて欲しいです!」
https://01intern.com/article/1989
有償/無償インターンの違いとポイント
インターンシップには、有償のものと無償のものがあります。
有償であることのメリットは、働いた分報酬が発生するので、モチベーションを保ちながら参加できることです。デメリットとしては、有償のインターンは長期にわたるものが多く、アルバイトのように「週〇日・〇時間」というように出勤回数が定められているものが少なくないという点です。学業や部活に支障が出ないように注意する必要があります。また、アルバイト禁止の高校に通っている場合、参加できない可能性があります。参加を検討する際は、担任の先生や生活指導室にアルバイト禁止の有無について確認してください。
無償のインターンのメリットは、短期間しか参加しなくて良いものが多く、学業や部活への支障が出にくい点です。しかしどれだけ働いても報酬が出ないため、目的意識など他の手段でモチベーションを保つ必要があります。
保護者・学校はどう考える?高校生インターンのサポート体制
ここでは、「親や先生にどう相談すればいい?」や「学校の許可は必要?」という疑問を持つ方に対して、保護者や学校が果たす役割について紹介します。
保護者の理解と協力が不可欠な理由
保護者の方は子どもの将来を誰よりも応援したいと思っています。しかし同時に、学業との両立や心身の健康、安全面など様々な心配事を抱えています。子どもの方は、保護者の方にインターンシップの重要性について丁寧に伝え、心配ではなく応援の方に気持ちを向けていきましょう。
また、保護者の方との対話では、感謝と尊重の姿勢で切り出してください。また、インターンシップについて、概要や参加したい理由、将来へのつながりなど丁寧に説明するようにしましょう。学業との両立や安全面・健康面などの懸念についても先回りして説明する事で、抱えている心配事を解消してあげましょう。また、保護者の方の意見を頭ごなしに否定するのではなく、きちんと聞く姿勢も大切にしましょう。
学校との連携で得られる支援とは?
学校経由で参加することには様々なメリットがあります。
まずは、信頼性と安全性です。学校は教育的な意義が薄く、労働環境に問題があるブラックインターンを排除し、生徒にとって本当に有益なプログラムを持つ企業を厳選しています。また、万が一インターンシップ先でトラブルが起きた際に、企業との間に入ってサポートしてもらえます。
次に手続きが簡素になります。複雑な応募書類の準備や手続きを学校がサポートしてくれたり、一括で取りまとめてくれたりする場合があります。これにより、学業と両立しながら効率的に準備できます。
担任の先生や進路指導室と連携することで、将来のキャリアについて客観的なアドバイスを受けたり、保護者への橋渡し役になってくれたり、企業へ取り合ってもらえたりすることもあります。
万が一のトラブル時の対応と安全性
考えられるトラブルの一つとして、仕事内容のトラブルが挙げられます。聞いていた仕事内容と違っていたり、高校生には危険・不適切と思われる作業を指示されたりする場合があります。その際は、現場の担当者にあらかじめ聞いていた仕事内容と食い違っていたり、指示された内容を遂行することが難しいことを伝えてください。
また、社員からパワハラやセクハラを受けるなど、人間関係のトラブルが発生した際は、すぐに担任の先生や進路指導室の先生、保護者に相談してください。身の危険を感じたら我慢せず、その場を離れても構いません。また、録音などの記録を取ったり、「いつ、どこで、誰に、何をされた(言われた)か」をメモしたりすることもおすすめです。
事故や体調不慮のトラブルが起こった際は、すぐに現場の責任者に報告をしましょう。また、学校と保護者に必ず連絡をしてください。また、もし事故が発生して会社に損害が発生した場合(例:会社のパソコンにコーヒーをこぼしてしまい、データが消えてしまった)、高額な損害賠償を請求される可能性があるので、あらかじめ損害賠償保険等に加入することもおすすめです。
将来のキャリアにつながるインターンの活用法
ここでは、「インターンって将来にどう生きるの」という疑問に答えるため、将来のキャリアに繋がるインターンの活用方法について解説します。
インターン経験を進路選択・面接・志望理由に活かす方法
インターン経験は進路選択に活かしたり、インターン経験を言語化することで、面接で志望理由として話したりすることができます。
インターンを通じて、自分にこの業種が向いているのか確認しましょう。他にも、自分の将来やりたいことや実現したいことに合っているのかどうかも確認しましょう。
また、インターンの経験を言語化することで、面接で志望理由を話す際に活かせます。その際は、「いつ」「どこで」「どのような経験」をして「どのように考え方が変わった」のか「何ができるようになった」のかを意識して話すことで、説得力があがります。
大学AO・総合型選抜での活用例
AO入試や総合型選抜では、「大学で何を学びたいのかが明確で、将来の目標に向かって主体的に行動できるかどうか」が重視されます。インターンシップ経験は、主体性や目的意識を証明するのに最適な材料です。インターン経験の話し方次第では、他にも学びたい分野への強い探究心や、課題発見・解決能力、コミュニケーション能力や協調性もアピールできます。
インターンシップ経験をアピールするには、まず「なぜそのインターンに参加したのか」「どのような活動をしたのか」「どのような課題や困難があったか」「その課題にどう向き合ったか」「結果的に何を学び、どう成長したか」を意識して話ましょう。場合によっては大学のアドミッションポリシーと繋げることで、さらに高い評価を得ることができます。
インターン経験から自分の興味を深めるには
インターン経験は、一過性で終わらせるのではなく、自己理解や学びの深化に繋げるようにしましょう。
まずはインターンに参加する前に、自分のインターンの参加動機を改めて確認し、その企業や業界に対する仮説を立てます。(例:この業界は〇〇だ。この企業は〇〇という事業を運営している等)そして、インターンを通じて学びたいことをリストアップして、試してみたい自分の強みも書き出してみましょう。
インターンが終わった後は、上記の事項を改めて確認し、仮説と現実とのギャップ、自分が実際何を学べたのか、自分の強みはどう発揮されて、他に強みや弱みが見られたのかリストアップして振り返るようにしましょう。
まとめ
今回は、高校生のインターンシップの概要、参加方法、トラブルの対処法、向き合い方などについて解説しました。インターンシップはもはや就活中の大学生だけのものではなく、高校生も将来の進路選択に利用するために、幅広く活用されています。もし将来の進路選択に迷っていたり、他の生徒が経験したことのない経験をしたいという場合は、一度検討してみればいかがでしょうか。

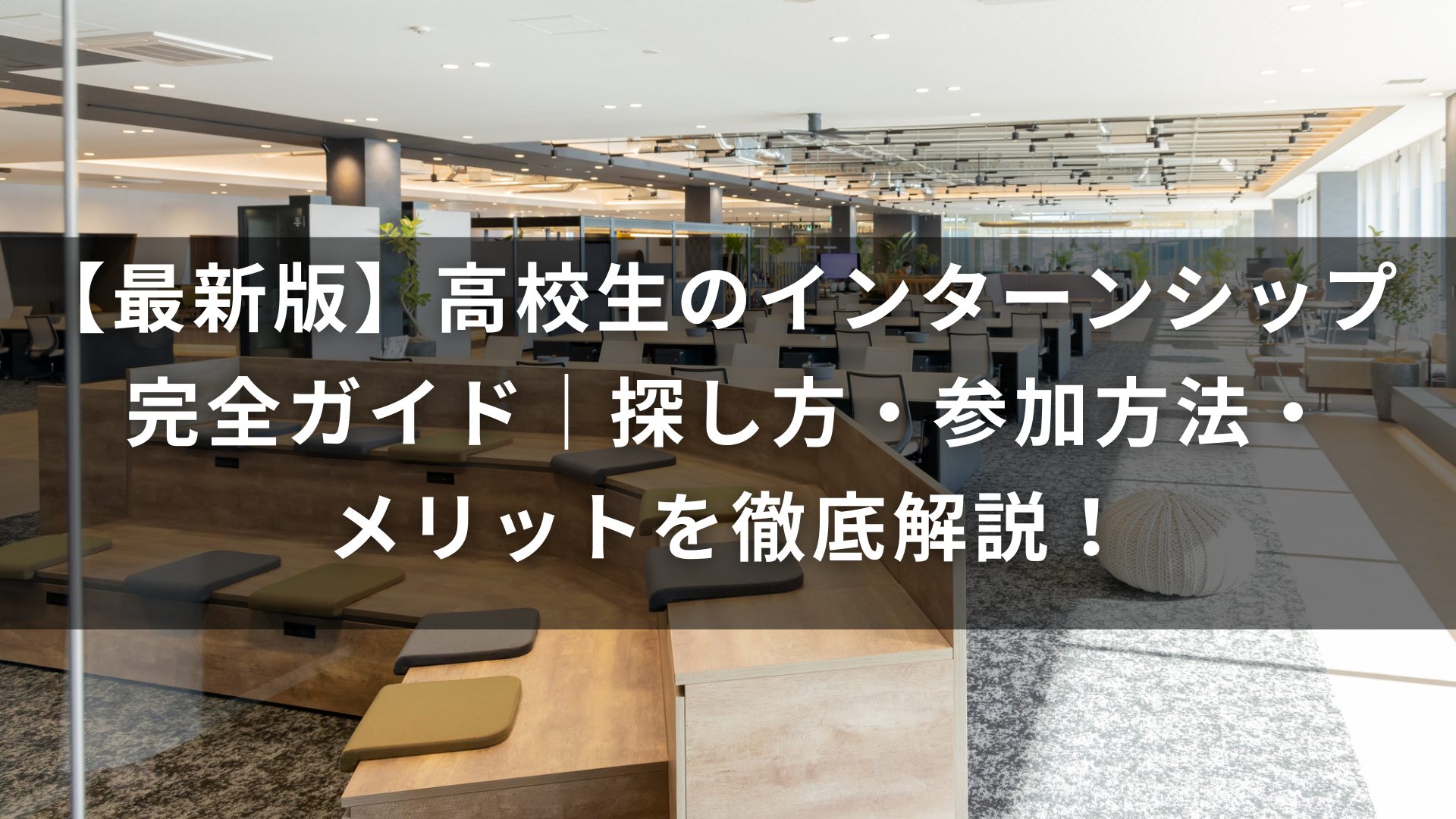
-1-320x180.jpg)

.jpg)
コメント